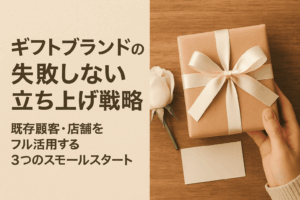お忙しい中、ご覧いただきありがとうございます。
ギフト通販業界で18年、バイヤー・商品企画として1,000社以上の食品会社様とお取引を重ね、数々のヒット商品を手がけてきました。
今は、その知見を活かし中小食品会社様のギフト事業を“売れる形”にするお手伝いをしている内田です。
今日は「EC参入」で陥る3つの罠と高収益ギフト事業への最短戦略についてお話しします。
- 0.1. EC参入と「見落とされがちな3つの壁」
- 0.1.1. この記事でわかること
- 1. なぜ食品ECには厳格な準備が必要なのか
- 1.1. 食品EC市場の現状と「信頼」という見えないコスト
- 1.2. 「実物を見られない」というECの根本的な課題
- 2. 食品ECを始める前に必須の「法律」と「届出」3つのポイント
- 2.1. 食品衛生法に基づく「営業許可」と「食品衛生責任者」
- 2.2. 消費者保護のための「特定商取引法」と「個人情報保護法」
- 2.3. お客様の「命」に関わる「食品表示法」の遵守
- 3. 「美味しそう!」を伝える画像(写真)の法則
- 3.1. 五感を刺激する「シズル感」の追求
- 3.2. 「不安を解消する」3つの比較写真
- 3.3. 背景ストーリーを伝える「安心素材」
- 4. 感覚的な美味しさを伝える「コピーライティング」の技術
- 4.1. 五感の代わりとなる「共感覚表現」を使う
- 4.2. お客様の「不安と願望」に寄り添う構成
- 4.3. 信頼性を高める「ストーリーテリング」
- 5. FAQ(よくある質問)と専門家からのアドバイス
- 5.1. Q1:自社のサイトを立ち上げるべきか、ECモールに出店すべきか?
- 5.2. Q2:SNSの画像とECサイトの画像は同じものでいいですか?
- 6. まとめ【EC成功の鍵は土台作り】
- 6.1. 次なる一歩へ:ECの土台を「高収益」に繋げるために
EC参入と「見落とされがちな3つの壁」
「コロナ禍以降、食品のEC市場は右肩上がりで、うちも早くネットで販売したい」「遠方のお客様にも、こだわりの商品を届けたい」「実店舗の売上減少をオンラインでカバーしたい」
もしあなたが、このような「ECへの期待」を抱きながらも、「何から手を付けていいか分からない」「法律や届出など、基本的なところで間違えたくない」という不安を感じているなら、その気持ちはよく分かります。
食品EC市場は、大手ECモールや産直サイトの台頭により、一見すると誰でも簡単に始められるように見えます。しかし、食品という「人の口に入る」特殊な商品を扱うがゆえに、他の商材にはない「3つの壁」が存在します。
- 【法律の壁】:食の安全を守るための複雑で厳格な法律(許可・表示義務など)
- 【信頼の壁】:実物を見られないネット販売で、いかに「安心」と「美味しさ」を伝えるか
- 【訴求の壁】:価格競争に陥らず、お客様の「食べたい」を刺激する表現力
この3つの壁をクリアせずにECを始めてしまうと、法律違反による営業停止という最悪の事態や、広告費だけがかさんで全く売れないというジリ貧状態に陥ります。
この記事でわかること
- 食品ECで絶対に違反してはならない「必須の法律と届出」の全体像がわかります。
- お客様の「安心したい」という心理を満たし、「美味しそう!」と思わせる商品写真(画像)の具体的な撮影ポイントと、NG例がわかります。
- 「感覚的な美味しさ」を言葉(コピー)で的確に伝え、商品の価値を正しく訴求するためのライティングの基礎を習得できます。
なぜ食品ECには厳格な準備が必要なのか
食品EC市場の現状と「信頼」という見えないコスト
EC市場全体が拡大する中で、食品分野のEC化率は年々上昇しています。しかし、その一方で、消費者庁や保健所によるネット販売への監視も厳しくなっています。
- 多くの消費者は、スーパーで買う商品については「安全」を前提としていますが、ネットで買う地方の食品については、「本当に安全か」「表示は正しいか」という根源的な不安を抱いています。
- 見えないコスト「法律リスク」
法律違反が発生した場合、社会的信用の失墜は免れません。特に食品業界において、一度失った信頼を取り戻すのは至難の業です。これは、事前のチェックを怠ることで発生する「見えない巨大なコスト」です。
中小食品メーカーにとって、大手に勝る「こだわり」を武器にするためには、まず「法律遵守」と「正確な情報提供」によって、お客様の不安を完全にゼロにすることが最優先事項となります。この土台がなければ、どんなに素晴らしい商品でも、クリックされることはありません。
「実物を見られない」というECの根本的な課題
実店舗であれば、お客様は商品を手に取り、匂いを嗅ぎ、試食することさえできます。しかし、ECではそれが不可能です。
この「実物を見られない」というECの根本的な課題を克服するため、「画像(視覚)」と「コピー(言語)」という2つの要素が、実店舗における「五感による体験」の代わり**を果たさなければなりません。
- 画像
「シズル感(美味しそうな質感)」や「鮮度、安全な梱包状態」を伝える唯一の手段。 - コピー
「味の複雑さ」「香り」「開発のストーリー」といった、画像だけでは伝えきれない「感情」や「価値」を伝える必須ツール。
この2つの要素が不十分だと、お客様は「なんとなく不安だから、無難な大手の商品でいいや」と離脱してしまいます。
食品ECを始める前に必須の「法律」と「届出」3つのポイント
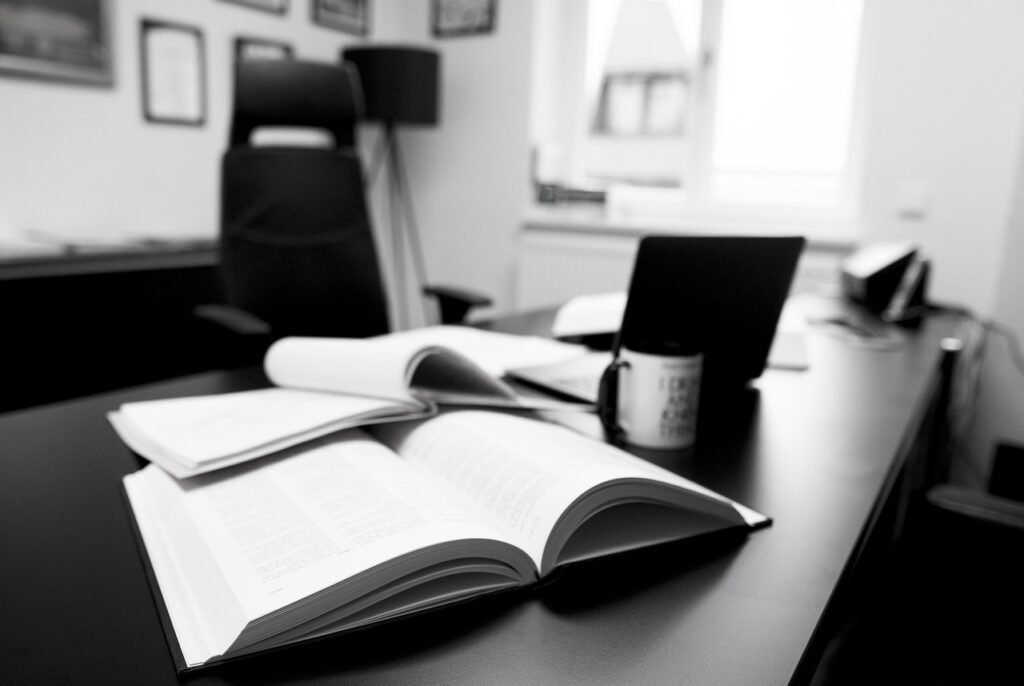
食品のネット販売を始めるために、まずクリアしなければならないのが「法律の壁」です。これは、後回しにできない絶対条件です。
食品衛生法に基づく「営業許可」と「食品衛生責任者」
あなたが自分で食品を製造・加工して販売する場合や、仕入れた食品を小分けにしたり、パッケージを詰め替えたりする場合は、食品衛生法に基づく「営業許可」が必要です。
- 許可の必要性
許可が必要な業種(菓子製造業、そうざい製造業、食肉販売業など)は、店舗の所在地を管轄する保健所によって定められています。 - 食品衛生責任者
営業許可を得る施設には、必ず「食品衛生責任者」を1名以上置くことが義務付けられています。これは、養成講習会を1日受講するか、調理師や栄養士などの資格があれば取得可能です。 - 施設の工事着工前に、必ず保健所に図面を持参して事前相談を行ってください。施設基準に適合しない場合、許可は下りません。
消費者保護のための「特定商取引法」と「個人情報保護法」
ECサイトで商品を販売する場合、特定商取引法(特商法)に基づき、以下の情報をお客様が見やすい場所に明記しなければなりません。
- 特商法表記の必須項目
会社名(事業者名)、代表者名、住所、電話番号、販売価格、送料、代金の支払い時期・方法、返品・交換の条件、商品の引渡時期など。 - 違反のリスク
これらが欠けていると、法律違反となり、お客様の信用も失います。必ず、お客様が不安なく取引できるように、正確に記載してください。
お客様の「命」に関わる「食品表示法」の遵守
食品ECで最も厳格なのが「食品表示法」の義務です。これは、お客様がアレルギーや健康状態に合わせて安全に商品を選択するために不可欠な情報です。
- 表示の必須項目:
- 名称(商品名)
- 原材料名(添加物を含む)
- 内容量
- 賞味期限/消費期限
- 保存方法
- アレルギー表示(特定原材料7品目とそれに準ずる21品目)
- 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
- ECでの注意点
ECサイトの商品ページにおいても、これらの情報をすべて正確に記載することが求められます。「ネットだから大丈夫」は通用しません。特にアレルギー表示は、命に関わるため、製造過程まで徹底した確認が必要です。
「美味しそう!」を伝える画像(写真)の法則
食品ECでは、お客様は画像を「試食の代わり」として見ています。ただ綺麗なだけでなく、「安心感」と「シズル感」の両方を伝えるための3つの法則を実践してください。
五感を刺激する「シズル感」の追求
- シズル感とは
焼きたての湯気、肉のテリ、野菜のみずみずしさなど、お客様の五感を刺激し、食欲をそそる質感のことです。 - 具体的な撮影
- 断面を見せる: ケーキやパン、具材の詰まった商品などは、必ず断面を撮り、中身の品質とボリュームを正直に伝える。
- 臨場感を出す: 煮込み料理ならフツフツとした泡、揚げ物なら衣のカリッと感が伝わるよう、接写(クローズアップ)を多用する。
- 自然光を活用: 暖かみのある自然光(窓際など)を使うと、食品の色味が鮮やかになり、美味しそうに見えます。
「不安を解消する」3つの比較写真
お客様がネットで食品を買う際に抱く最大の不安は**「サイズ感」「状態」「安全性」です。これらの不安を解消する画像を必ず用意します。
- サイズ比較写真
商品を手に持った写真や、身近なもの(卵、ペンなど)と並べた写真を撮り、お客様が届いたときの大きさを正確に想像できるようにします。 - 梱包状態の写真
「どのような箱で、どのように梱包されて届くか」の写真を載せ、配送中の破損や衛生面への不安を解消します。特にギフト商材では必須です。 - 調理・使用シーンの写真
「どうやって食べるのか」「どんな料理に使えるのか」という利用シーンを提案し、購入後のイメージを具体化させます。
背景ストーリーを伝える「安心素材」
- 実行方法
原材料の生産地の風景、製造者の真剣な顔、手作業の工程などを写真に撮り、商品ページに掲載します。 - 効果
これは、「誰が、どんな想いで、どのように作ったか」という信頼の根拠になり、大手メーカーの大量生産品にはない「安心」を提供できます。
感覚的な美味しさを伝える「コピーライティング」の技術
画像で「食べたい」と思わせたら、次はコピー(文章)で「この商品を買うべき理由」**を確信に変える必要があります。
五感の代わりとなる「共感覚表現」を使う
画像だけでは伝えられない「食感」「香り」「温度」といった感覚を、具体的な言葉で表現します。
- 食感
「もちもち」「とろけるような口どけ」「サクッとした歯切れの良い衣」「ザクザクとした食べ応え」 - 味
「口いっぱいに広がる芳醇な香り」「甘さがすっと引く、上品な余韻」「濃いのに飽きのこない深み」 - NG表現
「美味しい」「絶品」「最高」といった抽象的な言葉は、誰もが使っていて説得力がありません。「誰にでもわかる、具体的な表現」を徹底してください。
お客様の「不安と願望」に寄り添う構成
コピーライティングは、単なる商品説明ではなく、お客様の心の動きに寄り添うことが重要です。
- 問題提起
お客様が抱える「悩み」や「理想の食卓」を言葉にする。(例:「毎日のお弁当のおかずに悩んでいませんか?」「本当に体に良いおやつを子供にあげたい」) - 共感と解決
その悩みに共感し、あなたの食品がどう解決するかを提示する。(例:「無添加だから、安心して大切な人に贈れます」「湯煎で5分、忙しい日の夕食にプロの味が加わります」) - 確信と行動
「今すぐ買うべき理由」を提示し、購買を後押しする。(例:「今期の収穫分は残りわずかです」「ギフトに最適なラッピングを無料でお付けします」)
信頼性を高める「ストーリーテリング」
- 商品の開発に至った想い、原材料へのこだわり、地域や生産者との繋がりを、物語形式で語ります。
- 効果
ストーリーは、お客様に「ただの食品ではない、価値のあるもの」と感じさせ、価格競争から脱却する最大の武器となります。特にギフト商材では、「贈る相手に語れるエピソード」として大きな付加価値になります。
FAQ(よくある質問)と専門家からのアドバイス

Q1:自社のサイトを立ち上げるべきか、ECモールに出店すべきか?
A:初期は「ECモール」でテストし、最終的には「自社サイト」を目指すべきです。
- ECモール
集客力があるため、初期の市場テストや認知度向上に有効です。ただし、手数料が高いため、利益率は下がります。 - 自社サイト
利益率は高いですが、集客(SEO対策など)を全て自分でやる必要があります。 - 戦略
まずはモールで「売れる商品」と「お客様のニーズ」を掴み、利益率の高いギフト商品などを自社サイトで展開し、高収益化を目指すのが理想的です。
Q2:SNSの画像とECサイトの画像は同じものでいいですか?
A:役割が異なります。SNSは「興味喚起」に、ECサイトは「確信」のために使い分けてください。
- SNS
「ライブ感」や「楽しさ」を重視し、日常の風景や製造の舞台裏など、親近感を出す写真が有効です。 - ECサイト
「商品の正確な情報」「安心できる梱包状態」「シズル感の最高の状態」**を伝えるための、プロレベルの高品質な写真が必要です。
まとめ【EC成功の鍵は土台作り】
- 「営業許可」「食品表示法」など、お客様の安全と信用を守る絶対的な土台。
- 「シズル感」「安心感」を伝える、ECにおける試食の代わり。
- 食感」「ストーリー」を言語化し、お客様の購買意欲を確信に変える技術。
食品ECで成功する鍵は、華やかな集客テクニックではなく、この3つの土台を堅実に築くことにあります。この土台があれば、あなたのこだわりの商品は、必ず全国のお客様に届きます。
次なる一歩へ:ECの土台を「高収益」に繋げるために
さて、食品ECの法的な土台と情報発信の準備が整った今、次に考えるべきは「どうすれば価格競争を避け、高収益を確保できるか」という成長戦略です。
中小食品メーカーが高収益を目指す上で、「感情的価値が高く、価格競争に巻き込まれにくい」ギフト事業は最適な選択肢の一つです。
しかし、ギフト事業を成功させるには、ECの基礎とは別に「なぜうちの商品が贈り物として選ばれるのか」という根幹の価値を明確にする必要があります。
そのギフト事業の「成功の土台」が明確になっているかを客観的に把握するための無料チェックリストをご用意しました。
もし、あなたがECの次のステップとして、高収益なギフト事業を確立したいと考えているなら、現状を客観的に把握できる無料チェックリストをご活用ください。
課題が見えることで、次の一手も明確になります。未来の成果につなげるために、ぜひご活用ください。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
あなたのビジネスが成功することをいつも応援しています。