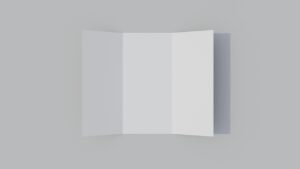お忙しい中、ご覧いただきありがとうございます。
ギフト通販業界で18年、商品企画・バイヤーとして1,000社以上の企業様とお取引を重ね、数々のヒット商品を手がけてきました。
今は、その知見を活かし食品メーカー様のギフト事業を“売れる形”にするお手伝いをしている内田です。
今日は「中小食品メーカーの売上を伸ばす!他業界に学ぶギフト通販の3つの新視点」についてお話しします。
- 1. なぜ、今あなたのギフト事業は「新しい視点」を必要としているのか?
- 1.1. この記事でわかること
- 2. ギフト市場の現状と「モノ」から「コト」への消費トレンド
- 2.1. 飽和した「モノギフト」と高まる「体験ギフト」ニーズ
- 2.2. なぜ問題が起きるのか?「業界の常識」に囚われた企画
- 3. 他業界のヒット事例から学ぶ「売上を伸ばす3つのヒント」
- 3.1. ヒント1:サブスクリプションモデルで「途切れない繋がり」を作る(IT・食品業界より)
- 3.2. ヒント2:モノではなく「特別な体験」を贈る価値に転換(旅行・サービス業界より)
- 3.3. ヒント3:ユーザー生成コンテンツで「信頼の輪」を広げる(美容・アパレル業界より)
- 3.4. あなたのギフト商品に「3つのヒント」を応用するチェックリスト
- 4. FAQ(よくある質問)と専門家からのアドバイス
- 4.1. Q1:サブスクは在庫管理が大変ではありませんか?
- 4.2. Q2:体験型ギフトは食品以外を扱うことになり、手間が増えるのでは?
- 4.3. Q3:SNSでのユーザー生成コンテンツ活用は、投稿がないと意味がないのでは?
- 4.4. 実行時の落とし穴とチェックポイント
- 5. まとめ【他業界から学んで「ギフトの常識」を打ち破る】
なぜ、今あなたのギフト事業は「新しい視点」を必要としているのか?
「他社がやっていないことをやらなければ…」と、新しい施策を模索していませんか?
しかし、新しいこと=売れるわけではありません。あなたの抱えるギフト通販の課題は、主に以下の点に集約されるのではないでしょうか。
- 差別化の壁
商品品質には自信があるのに、競合との違いが埋もれてしまい、価格競争から抜け出せない。 - リピートの壁
ギフトは単発の購入になりがちで、リピーターや継続的な売上に繋がらない。 - 付加価値の壁
「モノ」を売ることしかできておらず、「体験」や「感情」といった付加価値を上乗せできていない。
このままでは、あなたの素晴らしい商品も、市場の「常識」という枠の中に留まり、大きなブレイクスルーを生み出すことができません。
この記事でわかること
- 3つの成功法則
食品・ギフト業界の枠を超えた、他業界のヒット事例から抽出した売上を伸ばすための具体的な3つの戦略がわかります。 - 価格競争からの脱却
「モノ」ではなく「コト(体験)」を売る視点を身につけ、ギフトの単価と顧客満足度を同時に上げる方法がわかります。 - 実践的な応用
他業界の成功事例を、あなたの食品ギフトにいますぐ応用できる具体的なヒントとして持ち帰ることができます。
ギフト市場の現状と「モノ」から「コト」への消費トレンド
飽和した「モノギフト」と高まる「体験ギフト」ニーズ
日本のギフト市場は長年安定していますが、その中身が大きく変わっています。
- 高まる「体験」需要
旅行やレジャー、食事が制限された時期を経て、消費者は「物よりも記憶に残る体験」に対して高い価値を見出すようになりました。「心の豊かさ」や「人との繋がり」を贈る傾向が強まっています。 - SNS時代のギフト
購入者が選ぶ理由だけでなく、「贈られた人がSNSでシェアしたくなるかどうか」が、ギフトの選定基準に加わっています。ギフトは「個人的なやり取り」から「共感を呼ぶコンテンツ」へと変化しているのです。
なぜ問題が起きるのか?「業界の常識」に囚われた企画
多くの中小食品メーカー様が、ギフト企画でつまずくのは、「食品業界の常識」に囚われて、「商品の外側」にある価値を見逃しているからです。
- 常識1
「ギフト=高級な食品」:品質や素材を突き詰めることは大切ですが、それだけでは競合も同じ土俵にいます。お客様は、「なぜ、この高い食品をあえて選ぶのか」という、感情的な理由を探しています。 - 常識2
「販促はカタログで十分」:ギフトは年に数回の購入であるため、顧客との「継続的な接点」が作れず、リピートが生まれません。
これらの壁を打ち破るには、他業界で成功している「顧客との関係性」を作る手法を、あなたのギフト事業に応用することがカギになります。
他業界のヒット事例から学ぶ「売上を伸ばす3つのヒント」
他業界の成功事例は、あなたのギフト事業が価格競争から抜け出し、リピーターを獲得するための強力なヒントになります。
ヒント1:サブスクリプションモデルで「途切れない繋がり」を作る(IT・食品業界より)
【事例の概要】
IT業界のSaaS(Software as a Service)や、食品業界の定期便ボックスは、継続的に収益を生むサブスクリプションモデルで急成長しています。彼らは、「買い切りのモノ」ではなく「継続的な体験」を売っています。
【ギフトへの応用】
ギフト購入者と「贈られた人」の両方との「途切れない繋がり」を設計しましょう。
- リピートの仕組みを組み込む
一度ギフトを受け取った人(受取人)に対し、「お礼と感想を送ると、次回使えるクーポンがもらえる」仕組みを同梱物で設計し、受取人を次の購入者予備軍に変えます。 - 「テーマ型サブスク」
通常の定期購入ではなく、「毎月異なる地域の隠れた名産品を贈る」や「旬の食材に合わせたオリジナル調味料を贈る」といったテーマ型ギフトサブスクを導入し、ギフトの新たな需要を掘り起こします。
ヒント2:モノではなく「特別な体験」を贈る価値に転換(旅行・サービス業界より)
【事例の概要】
旅行業界や体験型サービスは、モノが存在しないにもかかわらず、「忘れられない思い出」という感情的な価値を売ることで高単価を実現しています。
【ギフトへの応用】
あなたの食品ギフトに、「特別な食体験」という付加価値を上乗せしましょう。
- 「ミールキット化」による体験
「ただの食材」ではなく、「三ツ星シェフ監修のレシピと調味料がセットになった、自宅で楽しむ特別なディナーキット」として販売し、単価と満足度を上げます。 - 生産者との繋がり体験
商品に「生産者とオンラインで交流できるチケット」や「工場見学の割引券」を同梱し、食の背景にある物語に触れる体験**を贈ります。これにより、価格以上の感情的価値が生まれます。
ヒント3:ユーザー生成コンテンツで「信頼の輪」を広げる(美容・アパレル業界より)
【事例の概要】
美容やアパレル業界では、企業広告よりも「一般の利用者のリアルな投稿(UGC)」が、信頼性と購買意欲を高める最大の要因になっています。
【ギフトへの応用】
贈られた人が「思わず自慢したくなる」ような仕掛けを作り、SNS上で信頼と認知の波及を狙いましょう。
- 「シェアしたくなる設計」
パッケージを開けるまでのワクワク感や、開けた後の写真映えする美しさ(例:花を添えたようなデザイン)を徹底的に追求します。 - ハッシュタグの活用
「#〇〇ギフト体験」「#心温まるおうち時間」といった、シェア促進型のハッシュタグを同梱物に明記し、投稿を促します。お客様が自発的に行う投稿は、最大の信頼性(E-E-A-T)に繋がり、広告費を使わずに新規顧客を獲得できます。
あなたのギフト商品に「3つのヒント」を応用するチェックリスト
あなたの主力ギフト商品に、この3つのヒントをどう応用できるか考えてみましょう。
| ヒント | あなたの商品のアイデア | 想定される効果 |
| サブスクモデル | 贈られた人が2ヶ月目以降を半額で試せる継続利用クーポンを同梱する | リピーターの獲得、2回目購入のハードルを下げる |
| 体験の提供 | 「美味しい食べ方動画」へのQRコードを同梱し、専門家のような食体験を提供する | 満足度向上、単価アップ(高付加価値化) |
| ユーザー生成コンテンツ活用 | 開けた時に「わぁ!」となるサプライズのメッセージカードを同梱し、SNS投稿を促す | 新規顧客へのリーチ拡大、信頼性の向上 |
FAQ(よくある質問)と専門家からのアドバイス

Q1:サブスクは在庫管理が大変ではありませんか?
A: 最初から複雑なシステムは不要です。まずは「年に2回の季節のギフト(お中元とお歳暮)」を対象に、「自動でご案内メールを送る仕組み」からスタートしましょう。
これにより、既存の在庫管理を大きく変えずに、リピート注文の手間を減らすことができます。小規模なシステム(例:Shopifyのアプリなど)から始めるのがおすすめです。
Q2:体験型ギフトは食品以外を扱うことになり、手間が増えるのでは?
A: 「食品の価値を高めるデジタルな体験」に絞りましょう。ワークショップチケットのような物理的なモノではなく、「オンライン動画コンテンツ」「レシピPDF」「生産者とのライブチャット権」など、「デジタルな付加価値」であれば、在庫や配送の手間を増やすことなく、ギフト単価を上げることができます。
Q3:SNSでのユーザー生成コンテンツ活用は、投稿がないと意味がないのでは?
A: 投稿を待つだけでなく、「投稿したくなる理由」を作りましょう。最も効果的なのは、「写真を撮りたくなる特別なパッケージ」と、「誰かに教えたくなるストーリー」です。
お客様が投稿してくれたら、必ずお礼のメッセージを送るなど、企業とお客様の温かい繋がりを見せることも、次の投稿を促す要因となります。
実行時の落とし穴とチェックポイント
| 実行時の注意点 | 詳細 |
| 価格設定の注意 | 「体験」や「サブスク」を導入する際は、必ず**「人件費」や「顧客対応費」も含めた正確な利益計算を行い、安易な価格競争に参入しないこと。 |
| ブランドの一貫性 | ユーザー生成コンテンツ活用などで「映え」を意識しすぎると、商品の持つ本来の品質や誠実さが薄れてしまいます。「安心・安全」という核となるメッセージからブレないように注意しましょう。 |
| 受取人の視点 | サブスクや体験型ギフトは、贈る人(購入者)だけでなく、贈られた人(受取人)が簡単に利用できるか、面倒ではないかという視点で設計しましょう。 |
まとめ【他業界から学んで「ギフトの常識」を打ち破る】
- 市場の変化
ギフト市場は「モノ」から「体験・感情」を贈る時代へと変化しています。 - 3つの戦略
サブスクモデルによる途切れない関係性、体験付加による高付加価値化、ユーザー生成コンテンツによる信頼の輪の拡大が、売上を伸ばす鍵です。 - 応用
他業界の成功法則を、あなたの食品ギフトにデジタルな付加価値として低コストで応用することで、価格競争から脱却できます。
あなた商品には、必ず「お客様の心を動かすストーリー」が秘められています。しかし、「うちの商品がギフト通販で本当に売れるか、最初の戦略設計は正しいのか」といった疑問が残っているかもしれません。
ネット通販で成功し、リピーターを増やすためには、「何を、誰に、どんな価値として売るか」というギフト企画の軸が最も重要です。この企画の軸がブレていると、どれだけ新しい施策を導入しても、結果を出すのは難しくなります。
そこで、あなたの会社の商品やブランドの現状に基づき、「市場で通用するギフト価値」を持っているかを客観的にチェックするための、【ギフト課題診断チェックリスト】をご用意しました。
課題が見えることで、次の一手も明確になります。
未来の成果につなげるために、ぜひご活用ください。
今日も最後までお読みいただき
ありがとうございました
あなたのビジネスが大成功することを
いつも応援しています。