
お忙しい中、ご覧いただきありがとうございます。
ギフト通販業界で18年、MD・バイヤーとして1,000社以上の食品会社様とお取引を重ね、数々のヒット商品を手がけてきました。
今は、その知見を活かし中小食品会社様のギフト事業を“売れる形”にするお手伝いをしている内田です。
今日は「中小食品メーカーの価格競争を断つ「ブランドブック」活用戦略」について、お伝えします。
- 1. リピートが止まるのは「言葉のブレ」が原因です
- 2. ブランドブックとは?本質と中小企業への適合性
- 3. リピートを生み出すブランドブック活用の3ステップ
- 3.1. ステップ1:ブランドの「芯」を見つける(言語化の徹底)
- 3.2. ステップ2:ブランドブックを「実務」に落とし込む(仕組み化)
- 3.3. ステップ3:ブランドを「体現」する(継続的な運用)
- 4. FAQ(よくある質問)と専門家からのアドバイス
- 4.1. Q1. ブランドブックはデザイナーに依頼すべきですか?
- 4.2. Q2. どんな項目をブランドブックに入れるべきですか?(実践チェックリスト)
- 4.3. Q3. 一度作ったブランドブックはどのくらいの頻度で見直すべきですか?
- 5. まとめ【ブランドブックは中小企業が持つべき最強の資産】
- 5.1. 今回のポイント
リピートが止まるのは「言葉のブレ」が原因です
「新規顧客は増えるが、リピートが安定しない」というお声をききます。単に「美味しい」「高品質」なだけでは、価格競争に巻き込まれてしまいます。一時的な売上はあっても、継続的なリピートには繋がりません。
では、成功している中小食品会社は何が違うのでしょうか?彼らは「選ばれる理由」を安定的に供給するブランドの軸を持っています。
実は、リピートが安定しない原因は、「商品の味」や「品質」ではありません。ほとんどの場合、「お客様に届くメッセージのブレ」が原因です。
例えば、SNSで「無農薬野菜へのこだわり」を強調して新規顧客を獲得したとします。しかし、次に届いたメルマガが「今月のセール情報」一色だったらどうでしょうか?
電話対応の担当者が無愛想な態度をとるかもしれません。お客様は「あれ?この会社、結局何が一番大事なの?」と戸惑いを覚えます。この一貫性の欠如が、信頼を損なってしまうのです。これがリピートを阻む最大の要因です。この問題を根本から解決するツールこそが、ブランドブックです。
中小企業の「熱意」や「こだわり」を、お客様の心に深く刻み込みます。安定的なリピートへと繋げるための具体的な活用法を徹底的に解説します。
この記事を読むことで、あなたの会社は「誰にでもできるリピート施策」から脱却できます。そして、「あなただから選ばれるブランド」へと進化する道筋が見えるはずです。
ブランドブックとは?本質と中小企業への適合性
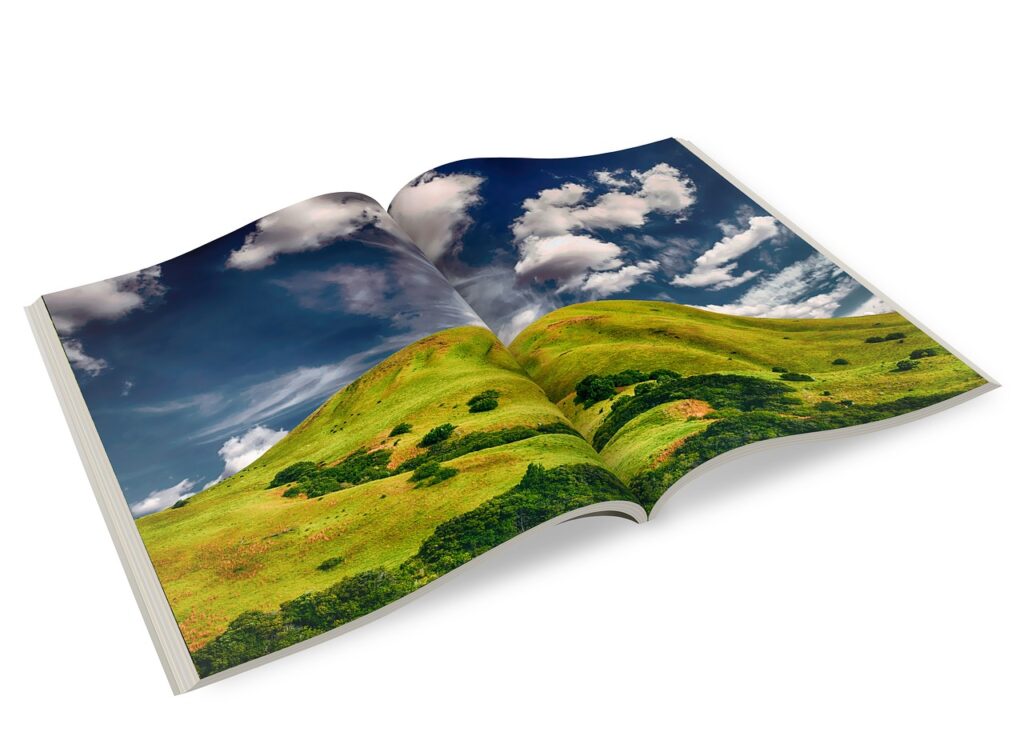
多くの方は「ブランドブック」と聞くと、「おしゃれなデザインガイド」をイメージするでしょう。しかし、それはブランドブックの「形」に過ぎません。
ブランドブックの本質は、「あなたの会社の哲学、約束、そして提供したい唯一の価値」です。これらを言語化し、体系的に整理した「会社の羅針盤」なのです。
中小食品会社がブランドブックを持つことは、大企業よりも重要です。大手のように、巨額の広告費でメッセージを押し通すことはできないからです。
中小企業は、「熱意」と「信頼」というアナログな資産で勝負しなければなりません。
ブランドブックは、その大切な資産をデジタルや実務に落とし込む仕組みです。全従業員がブレなく、一貫してお客様に届けられるようにします。
ブランドブックがない状態での失敗例があります。地方の老舗和菓子店のケースです。
社長は「伝統と素材の良さ」を最重要視していました。しかし、若手のEC担当者は「SNS映えする新商品」を推します。デザイナーは「都会的なおしゃれさ」を提案しました。
結果、商品もページデザインもコピーもすべてバラバラになりました。お客様は「結局、この店の良さは何?」と迷子になってしまいました。軸がないと、リソースが分散し、リピートへの道が閉ざされてしまうのです。
リピートを生み出すブランドブック活用の3ステップ
ブランドブックは作成して終わりではありません。重要なのは、それを「リピートを生む仕組み」として、日々の業務に落とし込むことです。
安定的なリピートを獲得するための活用ステップは、以下の3つに整理できます。
ステップ1:ブランドの「芯」を見つける(言語化の徹底)
すべての土台となる「会社の哲学」を徹底的に言語化します。これはデザインを決める以前の、最も重要な作業です。
- ミッション(存在意義)の定義
- 「なぜ私たちはこの商品を作るのか?」という根本的な問いに答えます。
- 「なぜ私たちはこの商品を作るのか?」という根本的な問いに答えます。
- ペルソナの再設定
- 誰にリピートしてもらいたいのかを明確にします。「贈る人」と「贈られる人」の両方を深く理解しましょう。
- 誰にリピートしてもらいたいのかを明確にします。「贈る人」と「贈られる人」の両方を深く理解しましょう。
- 提供価値の明確化
- 競合にはない、あなたの会社だけが提供できる「唯一の価値」を明確にします。
- 「おいしさ」だけでなく、「安心感」「ストーリー」「特別な体験」といった感情的な価値を含みます。
この芯が定まれば、「リピート顧客は、この価値に共感しているはずだ」という確信が持てます。
ステップ2:ブランドブックを「実務」に落とし込む(仕組み化)
言語化された「芯」を、EC業務の最前線にいるスタッフがブレなく実践できるようにマニュアル化します。
- トーン&マナーの統一
- お客様へのメール、メルマガ、SNSの「言葉遣い(トーン)」と「雰囲気(マナー)」を規定します。
- 特にクレーム対応時の言葉遣いこそ、ブランドの真価が問われる場所です。理念に基づいた対応の「型」を明確にします。
- 写真・デザインルールの設定
- ECサイトの写真は、「シズル感」を出すのか、「安心感」を出すのか、目的を明確にします。
- ブランドの哲学に合わない過度な加工や、安っぽく見える表現は禁止するルールを設けましょう。
- ギフト商品の写真には、必ず「贈るシーン」を想像させるカットを入れるガイドラインを設定します。
- 同梱物・メッセージの統一
- リピートを生む同梱物は、単なるチラシではありません。
- ブランドストーリーを記載した「読み物」や、社長からの「感謝のメッセージカード」などを同梱します。
- これらの文面やデザインも、ブランドブックで統一しましょう。
ステップ3:ブランドを「体現」する(継続的な運用)
ブランドブックは作って棚にしまうものではありません。日々の運用、つまり「社員全員によるブランドの体現」こそが、リピートを生みます。
- 社員教育と共有
- 新入社員はもちろん、ベテラン社員も含め、ブランドブックの内容を共有します。
- 日々の業務で迷ったときの「判断基準」として活用しましょう。
- 「彩子さん(ペルソナ)なら、この対応で喜んでくれるだろうか?」という視点を共通言語にします。
- 顧客体験のチェックリスト
- お客様の視点に立ち、「注文から開封までのすべての接点」をブランドブックに基づいてチェックします。
- 例:注文完了メールの文面、梱包の丁寧さ、開けた時の驚き、フォローメールの送信タイミングなど。
FAQ(よくある質問)と専門家からのアドバイス
Q1. ブランドブックはデザイナーに依頼すべきですか?
A. デザイナーに依頼する前に、まず「芯」を言語化してください。ブランドブックの価値は、そのデザインの美しさではありません。言葉の力にあります。
先にデザインを依頼すると、「おしゃれなだけの空っぽな本」になりがちです。
まずは、社長や社員が徹底的に議論しましょう。ミッションや価値観、ペルソナといった「芯」を自社の言葉で書き出すのが最優先です。
その後に、その芯を形にするためにデザイナーの力を借りるのが最も効果的です。
Q2. どんな項目をブランドブックに入れるべきですか?(実践チェックリスト)
A. リピートに必要な「一貫性」を生むための項目を優先しましょう。
中小食品会社が特に力を入れるべき項目は以下の通りです。
- ブランドの根幹:ミッション、ビジョン、コアバリュー(行動指針)、ブランドストーリー
- ペルソナ定義:「贈る人」と「贈られる人」の詳細設定
- トーン&マナーガイド:メール、電話、SNSでの具体的な言葉遣いと、避けるべき表現
- ビジュアルガイド:写真のルール(シズル感、光、背景)、ロゴの使用規定
- 顧客体験マニュアル:同梱物チェックリスト、フォローメールの送信タイミングと内容
Q3. 一度作ったブランドブックはどのくらいの頻度で見直すべきですか?
A. 市場やお客様の反応に応じて、最低でも年に一度は見直しましょう。
ブランドは生き物です。市場が変化し、お客様のニーズが変われば、ブランドの伝え方も進化させる必要があります。年に一度は、ブランドブックの内容と、実際の顧客の反応(レビュー、売上データ)を照らし合わせましょう。「芯」がブレていないか、伝え方が適切かを検証してください。
特に、新しい商品やサービスを開発する前には、必ずブランドブックに立ち戻りましょう。その商品がブランドの哲学に合致しているかを確認することが、失敗を防ぐ最大の注意点です。
【最大の注意点:理想と現実のズレを避ける】
ブランドブックを作る上で最も危険なのは、「理想のブランド像」を描きすぎることです。実態とかけ離れてしまうと、お客様は不信感を覚えます。ブランドブックは、「なりたい姿」だけでなく、「今お客様があなたをどう見ているか」という現実を反映させる必要があります。
まずは、お客様のレビューを徹底的に分析しましょう。そして、「すでに評価されている点」をブランドの強みとして言語化することから始めましょう。
まとめ【ブランドブックは中小企業が持つべき最強の資産】
「ブランド化は無理」と諦める必要はありません。中小食品会社が安定的にリピートをとるためには、大手にマネできない「哲学と熱意」を軸に据えることが必須です。
ブランドブックは、その哲学を社内で共有するための資産です。そして、すべての顧客接点で一貫して体現するための仕組みとなります。
今回のポイント
・リピート安定の鍵は「商品の味」ではなく「メッセージの一貫性」
・ブランドブックは、その一貫性を生み出す「会社の羅針盤」
・「芯の言語化」「実務への落とし込み」「継続的な体現」の3ステップ
・ブランドブックを軸にすることで、感情的な絆が生まれ価格競争から脱却
もし、あなたの会社が今、リピートの壁にぶつかっているなら、それは「ブランドの軸」が曖昧になっているサインかもしれません。
最後に、ギフト事業の現状を見える化する無料チェックリストをご用意しました。現状の課題をしてみませんか?
課題が見えることで、次の一手も明確になります。
未来の成果につなげるために、ぜひご活用ください。
今日も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
あなたのビジネスが成功すること
をいつも応援しています。


