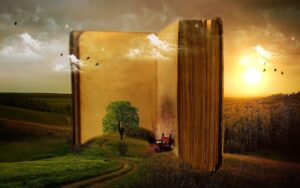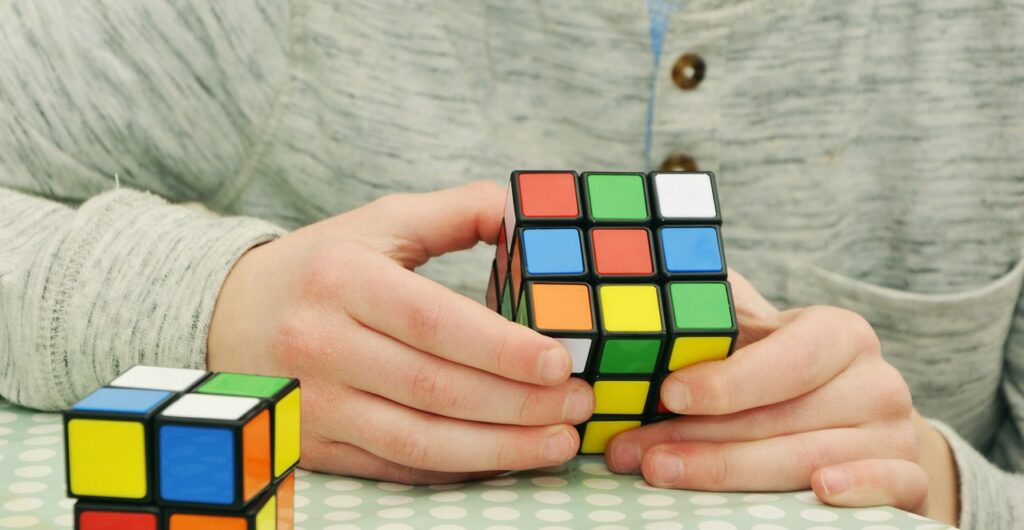
お忙しい中、ご覧いただきありがとうございます。
ギフト通販業界で18年、MD・バイヤーとして1,000社以上の食品会社様とお取引を重ね、数々のヒット商品を手がけてきました。
今は、その知見を活かし中小食品会社様のギフト事業を“売れる形”にするお手伝いをしている内田です。
今日は、「味には絶対の自信があるのに、なぜか思ったように売れない」という、テーマでお話しします。
味づくりや技術力に注力することは、ものづくりの原点として本当に素晴らしいことです。しかし、「おいしい=売れる」という単純な方程式は、残念ながら現代のギフト通販市場では通用しません。
- 1. 味が良いのに商品が売れない…?中小食品会社が抱える根本的な課題
- 1.1. 課題・悩みを明確化する3つの問い
- 1.2. 「いい商品=売れる商品」ではない現実
- 2. 専門家が解説!「売れない」を生む3つの落とし穴
- 2.1. 落とし穴1:自社目線の「生産ありき」設計
- 2.2. 落とし穴2:想定するお客様(ターゲット)が曖昧
- 2.3. 落とし穴3:ギフトならではの設計(付加価値)が欠けている
- 3. 組織内の「視点の分断」をなくす!「設計図」作成の重要性
- 4. 「設計図」で売上を伸ばした中小企業の成功法則
- 4.1. 【事例1】ターゲットとシーンを再設定し、高単価ギフトに成功した老舗佃煮メーカーB社
- 4.2. 【事例2】「伝わる価値」を設計し、リピート率を上げた手作りジャム工房D社
- 5. 売れるギフト商品を設計するための5つのチェックリスト
- 5.1. ステップ1:ペルソナ(誰に)とシーン(いつ)を明確にする
- 5.2. ステップ2:お客様の「伝達したい気持ち」を商品名とパッケージに反映する
- 5.3. ステップ3:ECサイトで「一瞬で伝わる」付加価値を設計する
- 5.4. ステップ4:価格設定に「付加価値の裏付け」を持たせる
- 5.5. ステップ5:開発・製造・販売の「情報連携」を習慣化する
- 6. FAQ(よくある質問)と専門家からのアドバイス
- 6.1. Q1:「ギフト特化に絞ると、一般のお客様を取りこぼしませんか?」
- 6.2. Q2:パッケージを豪華にすると、原価が上がって利益が出ませんか?
- 7. まとめ【行動こそが未来の成果を生む】
- 7.1. 今回のポイント
- 7.2. あなたに最初の一歩を踏み出していただくために
味が良いのに商品が売れない…?中小食品会社が抱える根本的な課題
まずは、あなたが今感じているであろう、具体的な課題や悩み、そしてその裏側にある構造的な問題から見ていきましょう。
課題・悩みを明確化する3つの問い
あなたが新商品や既存のリニューアルを進める際、無意識のうちに次のどれかに当てはまっていませんか?
- 「自信作なのに、在庫ばかりが積み上がっていく…」
自信をもって作った商品を並べたものの、季節イベントが終わっても売れ残ってしまい、廃棄ロスや倉庫保管コスト、そして最終的には大幅な値引き販売に追い込まれてしまう。結果、利益が残らず、また新しい開発に踏み出せない。 - 「商品紹介ページが、ただの“商品仕様書”になっている…」
ECサイトの商品写真や説明文が、「素材へのこだわり」「職人の技術」ばかりを強調し、「これを贈ると、相手にどんな良いことがあるのか?」というギフトならではの視点が抜け落ちてしまっている。 - 「繁忙期と閑散期の差が激しく、計画が立てられない…」
イベント直前に注文が集中するため、製造、梱包、発送で現場が混乱し、品質のバラつきや発送遅延といったクレームが多発する。一方で閑散期は手持ち無沙汰になってしまう。
これらの悩みの核心にあるのは、ただ一つ。それは、「お客様目線での『売り方』と『商品』の設計が分断されていること」です。
「いい商品=売れる商品」ではない現実
商品開発の現場では、「まずはいいものを作ろう」という発想が強く働くのは当然です。
しかし、特にギフト市場という特殊な環境では、味や品質よりも先に「誰に」「どんなシーンで」「どんな価値を届けるのか」という「設計図」が明確になっていることが、販売の前提になります。
この設計図が曖昧なまま進められた商品は、どれだけ手間暇かけても、お客様の心には響かないのです。
専門家が解説!「売れない」を生む3つの落とし穴

私がこれまでに多くの中小食品会社様とお付き合いして見つけた、「いい商品なのに売れない」状態を生んでしまう共通の「落とし穴」を、より深く掘り下げて解説します。
落とし穴1:自社目線の「生産ありき」設計
多くの場合、商品開発のスタート地点が「自社の都合」になっています。
- 「うちの既存の技術を活かすにはこの形状がいい」
- 「既存設備で作れるのはこの容量が限界」
- 「在庫を減らしたいから、賞味期限が長い商品にしよう」
たしかに生産効率やコストダウンは大事ですが、これはあくまで「自社で作れるもの」から逆算した発想です。
お客様はあなたの技術や設備を見るのではなく、「自分が必要としているもの」を探しています。「自社で作れるもの」と「お客様がほしいもの」の間にズレが生じた瞬間から、その商品は「売れない」宿命を背負ってしまうのです。
あなたの商品の出発点は、「お客様が抱えるギフトの悩みを解決すること」ですか? それとも「既存のリソースを活かすこと」ですか?
落とし穴2:想定するお客様(ターゲット)が曖昧
ギフト市場で成功するために最も重要なのは、「誰に向けて」その商品を作るか、です。
「誰に向けて作った商品ですか?」という質問に対して、「幅広い世代に…」「健康志向の方に…」と、ぼんやりした答えが返ってくることが少なくありません。これは、マーケティングの世界では「ターゲティングができていない」状態です。
ギフトの購入者は、自分のために買うのではなく、「大切な人」を喜ばせるため、または「義理や感謝」を伝えるために買います。
- ターゲットがぼやけている:誰の心にも刺さらない
- ターゲットが明確:深く、強く心に刺さる
「幅広い世代」を狙った商品は、結局誰にも選ばれません。なぜなら、30代のビジネスマンが上司に贈るギフトと、70代の祖父母が孫に贈るギフトでは、価格帯、パッケージデザイン、量、メッセージ性など、求められる設計が全く異なるからです。
【成功のためのペルソナ設定】 「誰に」を明確にするために、架空の理想的なお客様像(ペルソナ)を設定してみてください。
- 名前:田中美佐子(仮名)
- 年齢:42歳
- 職業:都内で働くメーカーの管理職
- 悩み:年に一度の取引先の社長へのお歳暮。形だけのものは避けたいが、選びに行く時間がない。センスが良いと思われたい。価格帯は5,000円〜7,000円。
このように具体的であればあるほど、「田中美佐子さんが迷わず買える設計」が見えてきます。
落とし穴3:ギフトならではの設計(付加価値)が欠けている
ギフト商品が店頭やECサイトで並ぶとき、まず問われるのは「味」ではなく、「パッと見て伝わる価値」です。
これは、商品名、パッケージ、写真、価格帯、セット内容、そして「メッセージ」といった、すべての要素によって構成される「シーンの提案力」です。
例えば、高品質なクッキーがあるとします。
- 「通常の設計」:クッキー20枚入り。3,000円。
- 「ギフトの設計」:【心からの感謝を伝える】プレミアム・アソートボックス。『お疲れ様』のメッセージカードを添えて。5,000円。
中身は同じクッキーかもしれませんが、後者の「ギフトの設計」は、購入者に「この商品なら、自分の伝えたい気持ちを代わりに届けてくれそう」という、情緒的な付加価値を与えます。この付加価値こそが、お客様が「定価で購入する決め手」となるのです。
組織内の「視点の分断」をなくす!「設計図」作成の重要性

なぜ、こうした「落とし穴」に陥ってしまうのでしょうか? その背景にあるのは、中小食品会社特有の「意識・視点の分断」です。
中小企業では、社長や数名の担当者が「商品開発(つくる)」と「マーケティング(売る)」を兼任しているケースがほとんどです。しかし、人が少ないからこそ、「意識や視点の分断」が起こり、商品設計に大きなズレが生じます。
例えば、今週は製造(つくる)に集中しているため、市場調査やECサイトの改善(売る)がおろそかになってしまう。または、「最高の味を作れば売れるはず」という『開発側の論理』と、「お客様はパッケージで選ぶ」という『販売側の現実』が、頭の中で切り替わらずに混在してしまうのです。
本来、ヒット商品には例外なく、ターゲット・シーン・訴求ポイント・見せ方まで、一貫した「売れる設計図」があります。この「設計図」こそが、開発・製造・販売のすべてを統合する羅針盤となり、「視点の分断」を解消する鍵となるのです。
この設計図をもとに商品を見直すことで、すでにある商品も改善して売れる可能性が高まります。
「設計図」で売上を伸ばした中小企業の成功法則
「設計図」が曖昧だったために失敗した商品が、設計図を見直しただけで、V字回復した事例を見ていきましょう。
【事例1】ターゲットとシーンを再設定し、高単価ギフトに成功した老舗佃煮メーカーB社
B社が抱えていた課題
長年、定番の佃煮セット(3,000円台)を販売していましたが、競合も多く、価格競争に巻き込まれていました。新商品の高級佃煮セット(6,000円)を開発しましたが、「高すぎる」と敬遠され、全く売れませんでした。
B社の「設計図」(解決策)
- ターゲットの再設定
「幅広い世代」を捨て、「退職祝いや法事など、格式ある場で贈る、本物志向の40~50代男性」にターゲットを絞り直しました。 - シーンの再設計
「法事のお供え」「お世話になった上司への御礼」というシーンに特化し、商品名を「感謝の想いを伝える【至高の味紀行】」に変更。 - パッケージの変更
これまで使っていたカジュアルな化粧箱から、重厚感のある木箱風パッケージと、高級感のある手漉き和紙の「のし」に変更。
得られた成果
- 価格帯に対する抵抗感が激減しました。お客様は「このパッケージとシーンなら6,000円はむしろ安い」と感じ、値下げなしで売上が安定しました。
- 高単価ギフトとしてECサイトの「贈答品」カテゴリーで上位表示されるようになり、競合との価格競争から完全に抜け出せました。
【事例2】「伝わる価値」を設計し、リピート率を上げた手作りジャム工房D社
D社が抱えていた課題
無添加・低糖質の手作りジャム(2,500円)は味が良いと評判でしたが、ECサイトでは「写真映えしない」「どこにでもあるジャム」と見なされ、初回購入だけで終わってしまうリピート率の低さに悩んでいました。
D社の「設計図」(解決策)
- 価値の再設計
「無添加」という抽象的な価値ではなく、「毎朝の食卓を彩る、罪悪感のない贅沢」というシーンとメッセージに落とし込みました。 - 商品名の変更
「低糖質ブルーベリージャム」から「【心と体にやさしい】朝のごちそうジャム・ブルーベリー」へ変更。 - 写真と提案の変更
「ジャムそのものの写真」から、「美しいモーニングプレートに、ジャムをスプーンでひとすくいしている、温かい食卓のイメージ写真」に変更。「レシピカード」を同梱し、ジャムを使った新しい食べ方を提案しました。
得られた成果
- 商品の持つ「健康」と「贅沢」という価値が一瞬で伝わるようになりしました。
- 同梱したレシピカードによって消費スピードが上がり、リピート購入のサイクルが早まりました。
- 単なる食品ではなく、「ライフスタイルを豊かにするもの」として認識され、リピート率が大幅に改善しました。
売れるギフト商品を設計するための5つのチェックリスト
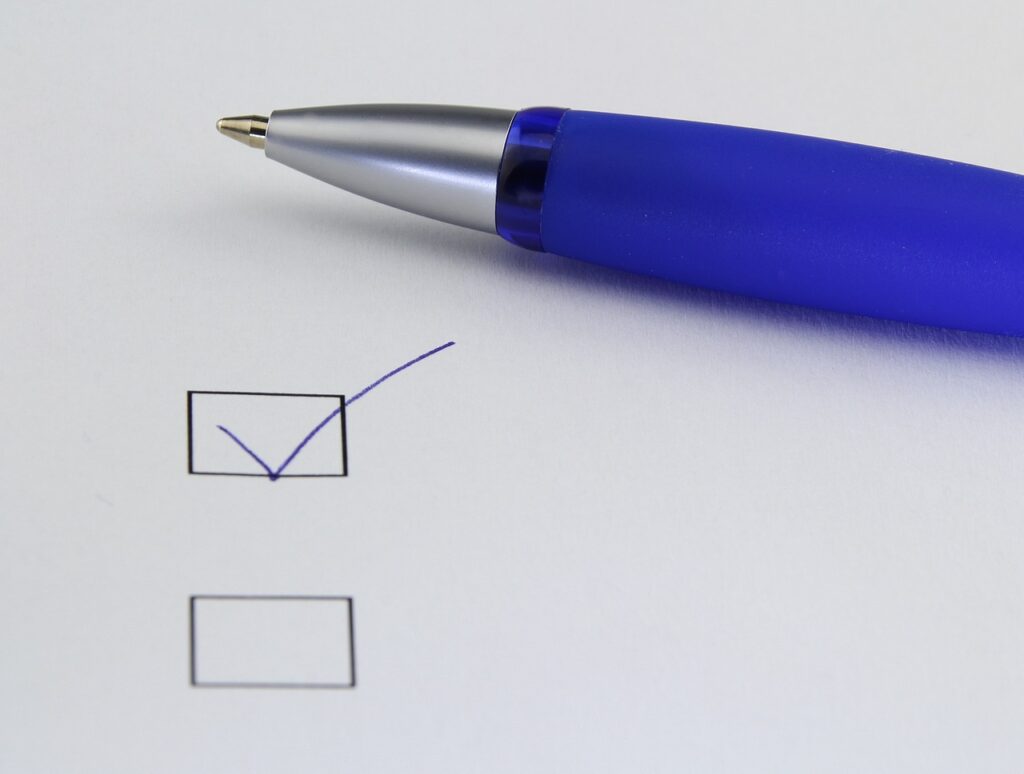
成功事例が示す通り、「売れる商品」は、センスや運ではなく、構造的に組み立てられています。
あなたの商品がこの「売れる設計図」を満たしているか、5つのステップで確認してみましょう。
ステップ1:ペルソナ(誰に)とシーン(いつ)を明確にする
「誰に」が曖昧な商品は、誰の心にも刺さりません。ペルソナを具体的に設定し、その人が「どんな場面で」「どんな気持ちを届けたいか」を定義します。
【チェックリスト】
- 贈る人(購入者)の年齢、職業、年収、贈る目的を具体的に設定しましたか?
- 贈られる人(受取人)の趣味、家族構成、ライフスタイルを具体的に想像しましたか?
- 「母の日」「お歳暮」「内祝い」「お詫び」など、どのシーンに最も適しているかを絞り込みましたか?
ステップ2:お客様の「伝達したい気持ち」を商品名とパッケージに反映する
お客様は、商品ではなく「気持ちを届けるための道具」としてギフトを選びます。その気持ちを、商品自体が代弁できるように設計します。
【チェックリスト】
- 商品名に「素材」や「技術」だけでなく、「感謝」「お祝い」「お疲れ様」といった感情を表す言葉を入れましたか?
- パッケージは、贈るシーンの格(カジュアルか、フォーマルか)に合っていますか?
- 贈答用の「のし」や「ラッピング」のサービスは、競合よりも心遣いが感じられるものになっていますか?
ステップ3:ECサイトで「一瞬で伝わる」付加価値を設計する
ECサイトでは、お客様は瞬時に次の判断を下します。「これは私が必要なものか?」「この価格で妥当か?」。これをクリアするための付加価値を設計します。
【チェックリスト】
- メイン画像は、商品そのものではなく、「その商品が食卓に並んだ時の感動的なシーン」を表現していますか?
- セット内容(量や種類)は、ペルソナの贈る相手にとって「多すぎず、少なすぎず」の最適なボリュームですか?
- キャッチコピーは、「誰でも作れる言葉」ではなく、あなたの会社の「独自のこだわり」が明確に伝わるものですか?
ステップ4:価格設定に「付加価値の裏付け」を持たせる
価格を少し高く設定する場合は、必ず「なぜ高いのか」という理由を、お客様が納得できる形で提示しなければなりません。
【チェックリスト】
- 価格に見合う「限定感」や「ストーリー」を提示できていますか?(例:〇〇職人の限定生産、〇〇農家との契約栽培など)
- 競合商品との違いを、「量や素材」ではなく「パッケージやメッセージ」といったギフト特有の付加価値で説明していますか?
- 送料や決済手数料を考慮した利益率が確保できる価格設定になっていますか?
ステップ5:開発・製造・販売の「情報連携」を習慣化する
「視点の分断」をなくすためには、社長が主導して、開発・製造・販売(EC担当)が定期的に集まる場を作り、「設計図」の共有を徹底します。
【チェックリスト】
- 新商品の企画会議に、必ず製造担当者とEC担当者を同席させていますか?
- お客様からのレビューやクレームを、開発・製造・販売の全員で毎月共有し、改善点を話し合っていますか?
- 商品のターゲットとコンセプトをまとめた「企画書」を、全担当者がいつでも確認できる状態にしていますか?
FAQ(よくある質問)と専門家からのアドバイス

ここからは、経営者・ご担当者様からよくいただく疑問にお答えし、さらに成功へ近づくための具体的な注意点をお伝えします。
Q1:「ギフト特化に絞ると、一般のお客様を取りこぼしませんか?」
A1: 心配いりません。ギフト商品として成功すれば、一般需要は後からついてきます。
ギフトで選ばれる商品は、「失敗が許されない」「安心できる」というお客様の信頼を勝ち取った証拠です。高い信頼性を持った商品は、ご自宅用や手土産にも自信をもって選ばれるようになります。まずはターゲットを絞り、ギフト市場での「絶対的な信頼」を勝ち取ることに集中してください。
Q2:パッケージを豪華にすると、原価が上がって利益が出ませんか?
A2: 「売れる設計図」ができていれば、原価増は問題ありません。
お客様は「メッセージを届けるためのパッケージ」にお金を払っているため、豪華にした分、販売価格に転嫁できます。重要なのは、原価率ではなく、粗利額と利益率です。パッケージにお金をかけたら、必ず「なぜこの価格なのか」という付加価値のストーリーをECサイトで伝えて、安易な値引きをしないことが肝心です。
まとめ【行動こそが未来の成果を生む】
今回のポイント
- 「売れる商品」は味の良さではなく、「設計図」で決まる
誰に、いつ、何を届けるかという設計がすべてを決定します。 - 成功のカギは「ペルソナとシーンの明確化」
ターゲットと贈るシーンを絞り込むことで、商品のメッセージ力が飛躍的に高まります。 - 「視点の分断」をなくす情報共有
開発、製造、販売の意識を統合し、一貫した商品設計を続けることが、事業を計画的に成長させます。
あなたに最初の一歩を踏み出していただくために
成功は、知っていることではなく、「行動に移すこと」から始まります。
「どこから手をつければいいのか?」「うちの商品設計の課題が具体的に何なのか、イマイチわからない…」と感じている経営者の方もいらっしゃるかと思います。
あなたのギフト事業の成功を確かなものにするために、まずは現状を客観的に把握することから始めませんか?
今すぐあなたのギフト事業の課題が3分で明確になる【無料ギフト事業 課題チェックリスト】を、ぜひご活用ください。
課題が見えることで、次の一手も明確になります。
未来の成果につなげるために、ぜひご活用ください。
今日も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
あなたのビジネスが成功すること
をいつも応援しています。