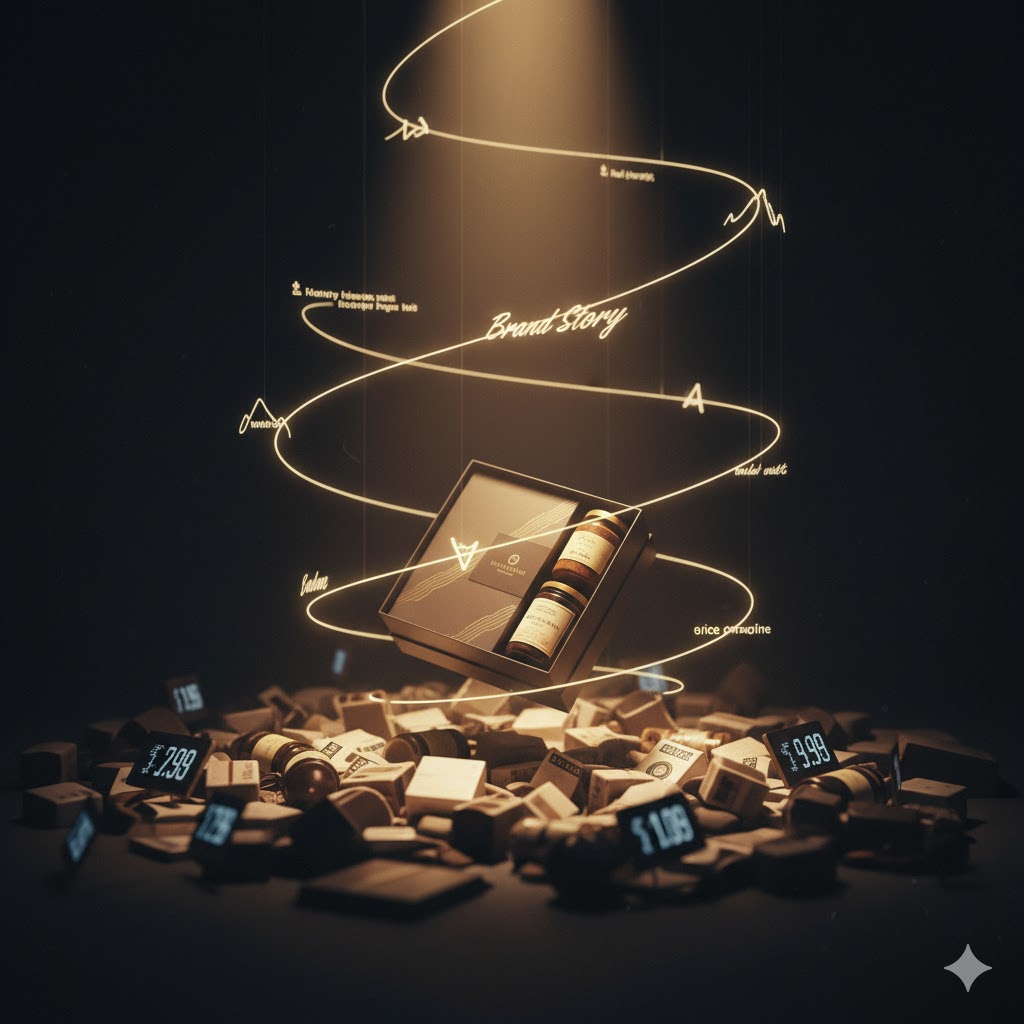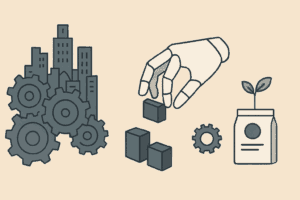「うちの商品はどこにも負けない自信作なのに、なぜか売れない」
「商談で『美味しい』とは言われるが、そこから先の話が進まない」
「競合他社に埋もれてしまい、価格競争に巻き込まれている」
もしあなたが、絶対の自信がある商品を持ちながらも、市場からの反応の薄さに歯がゆい思いをしているなら、その原因は「スペックの訴求不足」ではありません。
「社長であるあなたの『情熱』と『ストーリー』が、正しく言語化・発信されていない」ことにあります。
現代のギフト市場において、決定打となるのは「スペック」ではなく「共感」です。「なぜ、あなたがこの商品を作っているのか」という唯一無二の物語が伝わらない限り、商品はその他大勢の中に埋もれ続けます。
私はこれまでギフト・通販業界で15年以上、バイヤー・商品企画として1,000社以上の食品会社様の商品に携わってきました。現在はその知見を活かし、中小食品会社様のギフト事業を“売れる形”にするお手伝いをしています。
バイヤー時代、数多くの商品を見てきましたが、似たようなスペックが並ぶ中で採用の大きな決め手となったのは、社長の口から直接語られる「商品への真摯な想い」でした。
今日は「良い商品が売れない」を解決!社長の“情熱ストーリー”を発信し“販路拡大”すべき理由というテーマでお話しします。
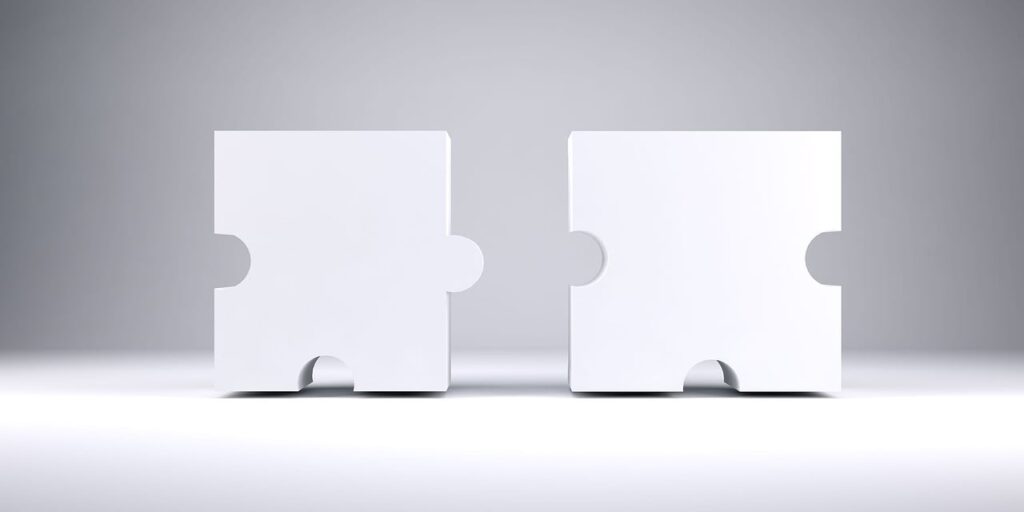
この記事でわかること
- 「良い商品」が売れない本当の理由が明確になり、現代のバイヤーや消費者が何を求めているのかが理解できます。
- 社長自身の「情熱」を最強の武器に変える方法。大企業には真似できないストーリーの言語化手順が手に入ります。
- 忙しい社長でも継続できる「発信の仕組み化」。属人化させずに、最小限の負荷で販路を拡大する3つのステップが分かります。
- 1. 「自信作」、なぜ市場に届かないのか?
- 1.1. 多くの社長が抱える「発信の壁」
- 2. なぜ「良い商品」が売れないのか?現代における「発信」の重要性
- 2.1. 「発信」の重要性とバイヤーの心理
- 2.2. なぜ「良い商品」を持つ社長ほど発信をためらうのか?
- 3. 社長の発信力を仕組み化し、継続的に情熱を届ける3つのステップ
- 3.1. ステップ1:発信の「核」となる「ストーリーと想い」を言語化する
- 3.2. ステップ2:無理なく継続できる「発信チャネル」と「頻度」を選ぶ
- 3.3. ステップ3:発信を「仕組み化」し、社長の負荷を最小限にする
- 4. FAQ(よくある質問)と専門家からのアドバイス
- 4.1. Q1:発信を始めたら、すぐに効果が出ますか?
- 4.2. Q2:何をどこまで話していいのか迷います。企業秘密のようなことはどうすれば?
- 4.3. Q3:SNSの「炎上」が怖くて発信できません。どうすれば良いですか?
- 4.4. Q4:BtoBの取引先に向けた発信と、BtoCの消費者に向けた発信は変えるべきですか?
- 4.5. Q5:発信を仕組み化しても、社長の「個性」が薄れてしまいませんか?
- 5. まとめ【発信力こそが、あなたの「良い商品」を世に送り出す最大の武器】
- 5.1. 次なる一歩へ【「良い商品」を“売れる形”に変えるための第一歩】
「自信作」、なぜ市場に届かないのか?

先ほどお伝えした通り、どんなに素晴らしい商品でも、その魅力が消費者に伝わらなければ存在しないのと同じです。
特に現代は情報過多の時代。ただ置いてあるだけ、ただチラシを配るだけでは、あなたの商品の真価は埋もれてしまいます。
特にBtoBバイヤーは、ウェブサイトやSNSで事前に情報収集する際、単なる商品情報だけでなく、社長自身の情熱、企業のストーリー、そして信頼性を発信から読み取ろうとしています。これは、彼らが新しい取引先を選ぶ上で非常に重要な判断基準となるからです。
多くの社長が抱える「発信の壁」
「発信する時間がない」
「何を話せばいいか分からない」
「SNSは若い人のものだと思っている」
「営業は得意だが、言葉で伝えるのは苦手」
—このような悩みを抱えている社長は少なくありません。
商品開発には熱心でも、その裏にある「情熱やストーリーを『発信』」することに消極的になりがちです。しかし、この「発信の壁」こそが、あなたの「良い商品」が世に出るのを阻んでいる最大の要因なのです。
なぜ「良い商品」が売れないのか?現代における「発信」の重要性

現代の消費者は、単に「良い商品」を求めているのではありません。
彼らは、商品の背景にある「ストーリー」や「作り手の情熱」、そして「企業としての信頼性」を重視しています。
特に中小食品メーカーにとっては、大企業には真似できない「顔の見えるモノづくり」こそが最大の武器となります。
「発信」の重要性とバイヤーの心理
- 購入意思決定への影響
複数のマーケティング調査や市場分析によると、消費者は、自分が共感できるブランドから購入したいと考えており、特に食品においては「ストーリー性」が購買意欲を大きく左右します。この傾向はBtoBでも同様で、バイヤーは単なるスペック比較だけでなく、「共感できる企業」との取引を望みます。 - SNSの影響力
消費者行動に関する調査では消費者の約70%がSNSでの情報が購入に影響を与えると回答しており、特に食品やギフトのようなパーソナルな商品では、共感や信頼が購買の決め手になります。BtoBバイヤーも、商談前に社長や企業のSNSをチェックし、「どんな人物が、どんな想いで事業をしているのか」を探ります。 - BtoB取引の変化
BtoBのバイヤーも、ウェブサイトやSNSで事前に情報収集を行うのが当たり前です。単なる商品スペックだけでなく、企業の理念や社長の顔が見える情報が、商談の成約率を高める要因となっています。社長が直接発信するメッセージは、企業の信頼性と透明性を高め、バイヤーに安心感を与えます。これは、新規取引開始の大きな後押しとなるのです。
なぜ「良い商品」を持つ社長ほど発信をためらうのか?
社長が発信に消極的になる理由はいくつかあります。
- 「忙しい、時間がない」という物理的制約
日々の経営、商品開発、営業、人材育成…と、社長業は多忙を極めます。発信活動は「後回し」になりがちです。しかし、この「後回し」が、実は最も大きな機会損失を生んでいます。 - 「何を話せばいいか分からない」という情報整理の壁
自分のこだわりや情熱は当たり前すぎて、「話す価値があるのか?」と感じてしまう。あるいは、どこから手をつけて良いか分からない。この「情報過多」の中での「情報の整理術」が求められます。 - 「発信するリスク」への懸念
批判されることへの恐れ、情報漏洩の不安、SNSの炎上リスクなどを考えると、発信にブレーキがかかります。しかし、リスクを必要以上に恐れるあまり、最大のチャンスを逃しているケースも少なくありません。 - 「発信は専門家の仕事」という思い込み
広報やマーケティングは外部に任せるもの、あるいは専門部署の仕事だと考え、社長自身が直接発信することの重要性を見過ごしています。しかし、社長にしか語れない「一次情報」の価値は、計り知れません。 - 「発信の効果が見えにくい」というモチベーションの壁
すぐに売上に繋がるわけではないため、継続するモチベーションを保ちにくいと感じてしまう。発信は短期的な戦術ではなく、長期的なブランド構築の投資です。
これらの壁は、決して社長が怠けているわけではありません。むしろ、真面目に商品と向き合っているからこそ、発信の優先順位が下がってしまうという皮肉な現実があります。
しかし、この壁を乗り越えない限り、あなたの「良い商品」は永遠にその真価を発揮できないまま終わってしまうかもしれません。
社長の発信力を仕組み化し、継続的に情熱を届ける3つのステップ

社長の忙しさや苦手意識を乗り越え、効果的な発信を継続するための「仕組み化」が重要です。ここでは、社長が無理なく発信を続け、その情熱を売上に繋げるための3つのステップをご紹介します。
ステップ1:発信の「核」となる「ストーリーと想い」を言語化する
発信する内容に困る社長が多いのは、「何を発信すべきか」が明確になっていないからです。まずは、あなたの会社と商品独自の「核」を言語化しましょう。
- 「なぜ、この商品を作るのか?」原点と情熱の深掘り
- 創業のきっかけ、商品開発の背景、その商品にかける一番のこだわりは何ですか?
- どんな困難を乗り越えてきましたか?(例:原料調達の苦労、失敗からの学び)
- その商品を「誰に」「どうなってほしい」と願っていますか?(例:家族の食卓を豊かに、アレルギーに悩む子どもたちにも安心を)
- ワーク
創業時の写真や、一番苦労した時の記録を見ながら、当時の感情をメモに書き出してみてください。それが最も響くストーリーの源泉です。同時に、商品開発ノートや日報を見返し、具体的なエピソードを掘り起こしましょう。
- 創業のきっかけ、商品開発の背景、その商品にかける一番のこだわりは何ですか?
- 「お客様に提供したい価値」を明確にする
- あなたの会社の商品は、お客様にどんな「体験」や「解決策」を提供しますか?(単に「美味しい」だけでなく、「家族団らんのひととき」「大切な人への感謝」「健康的で安心な食生活」など)
- 競合にはない、あなたの商品独自の魅力は何ですか?(例:地域限定の希少な原料、特許製法、徹底した手作り工程)
- ワーク
既存のお客様の声やアンケート、レビューを徹底的に見直し、お客様があなたの商品のどこに価値を感じているかを再発見しましょう。お客様が使う「生の声」が、あなたの商品の独自の魅力をより明確にしてくれます。
- あなたの会社の商品は、お客様にどんな「体験」や「解決策」を提供しますか?(単に「美味しい」だけでなく、「家族団らんのひととき」「大切な人への感謝」「健康的で安心な食生活」など)
- 「伝えるべきキーワード」を抽出する
- 深掘りした内容から、あなたの情熱やストーリーを最も端的に表す言葉(例:「匠の技」「無添加」「地域活性」「笑顔を育む」「健康志向」「サステナブル」など)をいくつか選定します。これらが、今後の発信の軸となり、SEO対策の基盤にもなります。
- 深掘りした内容から、あなたの情熱やストーリーを最も端的に表す言葉(例:「匠の技」「無添加」「地域活性」「笑顔を育む」「健康志向」「サステナブル」など)をいくつか選定します。これらが、今後の発信の軸となり、SEO対策の基盤にもなります。
【あわせて読みたい】
ステップ2:無理なく継続できる「発信チャネル」と「頻度」を選ぶ
社長が「継続できない」と感じる最大の理由は、「完璧を目指しすぎる」ことにあります。まずは「これならできる!」と思える最小限のチャネルと頻度から始めましょう。
- 「自社に合った」発信チャネルを選ぶ
- ウェブサイトのブログ・お知らせ欄
最も基礎的で、SEOにも貢献します。社長の想いをじっくり伝えられ、企業の公式情報として信頼性が高いです。「社長メッセージ」「開発秘話」などのカテゴリーを設けてみましょう。 - SNS(Facebook/Instagram/X(旧Twitter)など)
ターゲット層が多く利用しているSNSを選びましょう。写真や動画で視覚的に訴えやすく、日々の様子を気軽に発信できます。BtoBバイヤーもSNSを情報源とすることが増えています。 - メールマガジン/LINE公式アカウント
既存顧客や見込み客に直接情報を届けたい場合に有効です。限定情報や先行予約など、特別感を演出できます。 - YouTube/TikTok(動画)
社長の「人柄」や「熱意」が最も伝わりやすいですが、編集の手間がかかります。商品の製造工程や、社長自ら調理する様子などは視覚的に訴求力が高く、バイヤーにとっても魅力的な情報源になります。 - 選択基準
「誰に伝えたいか」「どんな情報を伝えたいか」「継続できる手間か」の3点で選びます。
全てに手を出さず、まずは1つか2つに絞りましょう。特にBtoBならウェブサイトのブログとFacebook、BtoCならInstagramがおすすめです。選んだチャネルでの競合他社の発信状況も確認し、差別化ポイントを見つけましょう。
- ウェブサイトのブログ・お知らせ欄
- 「無理のない」発信頻度を設定する
- 週に1回、月に2回など、必ず守れる頻度で設定します。「毎日投稿」などと意気込みすぎると、すぐに挫折します。
量より質、そして何より継続することが重要ですし、Googleの評価も継続性を重視します。決めた頻度を1年間守り続けることができれば、必ず効果が見えてきます。
- 週に1回、月に2回など、必ず守れる頻度で設定します。「毎日投稿」などと意気込みすぎると、すぐに挫折します。
- 「発信カレンダー」を作成する
- 年間や月間のスケジュールに、発信テーマとチャネルを落とし込みます。例えば、「〇月〇日:商品Aの開発秘話(ブログ)」「〇月〇日:製造現場の様子(インスタグラム)」など。季節イベントや新商品の発売時期に合わせてテーマを設定すると、より効果的です。
- 年間や月間のスケジュールに、発信テーマとチャネルを落とし込みます。例えば、「〇月〇日:商品Aの開発秘話(ブログ)」「〇月〇日:製造現場の様子(インスタグラム)」など。季節イベントや新商品の発売時期に合わせてテーマを設定すると、より効果的です。
ステップ3:発信を「仕組み化」し、社長の負荷を最小限にする
社長が直接全ての発信を行うのは非現実的です。チームや外部のリソースを活用し、社長の負担を減らしながら継続できる仕組みを作りましょう。
- 「社長は話すだけ」、記録は「任せる」
- 社長が話した内容を、スタッフが録音・録画し、テキスト化する役割を担います。例えば、週に30分だけ時間を設け、商品への想いや最近あったエピソードをスタッフに語りかける時間を設けます。この際、「インタビュー形式」にすると、社長も話しやすく、スタッフも質問を通じて深掘りできます。
社長の貴重な時間は「アイデア出し」と「話す」ことに集中させ、その後の「編集」「加工」「投稿」は任せる体制を築きましょう。これにより、社長の負担を大幅に軽減できます。
- 社長が話した内容を、スタッフが録音・録画し、テキスト化する役割を担います。例えば、週に30分だけ時間を設け、商品への想いや最近あったエピソードをスタッフに語りかける時間を設けます。この際、「インタビュー形式」にすると、社長も話しやすく、スタッフも質問を通じて深掘りできます。
- 「素材のストック」を習慣化する
- 日々の業務の中で、「これは発信に使えるな」と感じる瞬間(例:新しい食材の仕入れ、試作の様子、お客様の笑顔、社員の頑張りなど)があれば、スマホで写真を撮る、簡単なメモを残すなどを習慣化します。後で編集や加工ができるよう、高画質で保存することを心がけましょう。
- 日々の業務の中で、「これは発信に使えるな」と感じる瞬間(例:新しい食材の仕入れ、試作の様子、お客様の笑顔、社員の頑張りなど)があれば、スマホで写真を撮る、簡単なメモを残すなどを習慣化します。後で編集や加工ができるよう、高画質で保存することを心がけましょう。
- 「発信のテンプレート」を用意する
- 投稿の型(例:「【商品紹介】〇〇の魅力と簡単レシピ」「【社長のつぶやき】今日の発見と感謝」「【製造秘話】この一手間が味の決め手」)を決めておけば、内容を考える負担が減ります。キャッチコピーやハッシュタグのテンプレートも用意しておくと良いでしょう。
完璧な文章を目指す必要はありません。社長自身の言葉で、心を込めて伝えることが何よりも大切です。形式よりも「社長自身の声」が伝わることを重視しましょう。
- 投稿の型(例:「【商品紹介】〇〇の魅力と簡単レシピ」「【社長のつぶやき】今日の発見と感謝」「【製造秘話】この一手間が味の決め手」)を決めておけば、内容を考える負担が減ります。キャッチコピーやハッシュタグのテンプレートも用意しておくと良いでしょう。
- 「外部パートナー」の活用
- もし社内にリソースがない場合、ライター、SNS運用代行、動画編集者などの外部パートナーに一部を依頼することも有効です。特に専門的な編集やSEO対策などはプロに任せることで、品質の高いコンテンツを効率的に制作できます。
外部パートナーを使う場合でも、社長の「声」や「想い」がブレないよう、密な連携と定期的なフィードバックは不可欠です。パートナーに「社長の分身」となってもらうくらいの意識でコミュニケーションを取りましょう。
- もし社内にリソースがない場合、ライター、SNS運用代行、動画編集者などの外部パートナーに一部を依頼することも有効です。特に専門的な編集やSEO対策などはプロに任せることで、品質の高いコンテンツを効率的に制作できます。
この3つのステップを踏むことで、社長は自分の情熱を無理なく発信し続け、その結果、商品の価値が市場に正しく伝わり、売上へと繋がるでしょう。
FAQ(よくある質問)と専門家からのアドバイス

Q1:発信を始めたら、すぐに効果が出ますか?
A:いいえ、即効性のあるものではありません。 発信は「信頼貯金」のようなものです。地道に継続することで、徐々に認知度が上がり、信頼が構築され、半年から1年後に大きな効果として現れることが多いです。焦らず、まずは「継続すること」に集中してください。Googleの検索エンジンも、短期的な小手先のSEO対策よりも、長期的な良質なコンテンツの蓄積を重視します。
Q2:何をどこまで話していいのか迷います。企業秘密のようなことはどうすれば?
A:企業秘密や機密情報は絶対に開示しないでください。 発信する内容は、「商品の背景にある情熱」「製造過程のこだわり(具体的な製法ではなく、その心意気)」「社長の人柄や考え方」「日々の発見や感謝」「社員の働きがい」といった、企業の魅力や人間性を伝える部分に限定しましょう。バイヤーも消費者の求めているのは、レシピやコスト情報ではなく、「信頼できるパートナーとしての情報」です。どこまでが公開可能で、どこからが機密情報かを事前に社内で明確なガイドラインを設けることをお勧めします。
Q3:SNSの「炎上」が怖くて発信できません。どうすれば良いですか?
A:炎上を完全に避けることは難しいですが、リスクを最小限に抑えることは可能です。
- ネガティブな発言や、特定の政治・宗教的な内容、個人的な誹謗中傷は絶対に避ける。
- 情報の正確性に細心の注意を払い、誇大広告にならないようにする。
- 一度投稿する前に、複数の目で内容をチェックする。 特に、誤解を招く表現がないか、倫理的に問題がないかを確認します。
万が一炎上してしまった場合は、速やかに誠意ある対応(事実確認、謝罪、訂正、説明など)を行う準備をしておくことが重要です。リスクを恐れすぎて発信しないことの方が、ビジネスチャンスを失うリスクは大きいと認識しましょう。透明性を持って対応することが、逆に信頼を高める結果に繋がることもあります。
Q4:BtoBの取引先に向けた発信と、BtoCの消費者に向けた発信は変えるべきですか?
A:基本的な「想い」は共通ですが、伝え方、表現、そしてチャネルはターゲットに合わせて最適化すべきです。
- BtoB向け
信頼性、安定供給、製品の優位性、導入メリット(成功事例)、そして社長の経営哲学や会社としてのビジョンを強調しましょう。ウェブサイトのブログ、LinkedIn、Facebook、業界専門メディアへの寄稿などが有効です。バイヤーは、企業の事業継続性やパートナーとしての信頼性を強く意識します。 - BtoC向け
商品の美味しさ、利用シーン、健康効果、作り手のこだわり、感情的な体験を重視しましょう。InstagramやX(旧Twitter)、YouTube、TikTokなどが有効です。また、親しみやすい言葉遣いが求められます。 しかし、根本にある「社長の情熱」は共通のメッセージとして、どちらのチャネルでも響くはずです。ターゲットに合わせて「翻訳」するイメージです。
Q5:発信を仕組み化しても、社長の「個性」が薄れてしまいませんか?
A:いいえ、むしろ社長の個性を際立たせることができます。 仕組み化は、社長が苦手な作業や時間のかかる作業を効率化するためのものです。社長は「話す」「アイデアを出す」といった最も得意で、個性が出る部分に集中できるため、発信するコンテンツはより社長らしさを強く反映したものになります。社長の「肉声」をいかにコンテンツに落とし込むかが、仕組み化の成功の鍵です。
まとめ【発信力こそが、あなたの「良い商品」を世に送り出す最大の武器】
この記事では、「良い商品」が売れない原因が社長の「発信力」にあることをお伝えし、その発信力を仕組み化するための3つのステップをご紹介しました。
重要なのは、次の3点です。
- 社長の「情熱とストーリー」を言語化し、発信の「核」を明確にすること。 これが、バイヤーや消費者の心を掴むための第一歩です。
- 無理なく継続できるよう、自社に合った発信チャネルと頻度を選び、完璧を求めすぎないこと。 継続こそが信頼を築きます。
- 「社長は話すだけ」という仕組みを作り、発信の負荷を最小限に抑えながら継続すること。 社長自身の「声」を最大限に活かす工夫が不可欠です。
どんなに素晴らしい商品でも、その価値が伝わらなければ、市場にとっては存在しないのと同じです。
社長であるあなたの内側にある「情熱」と「ストーリー」は、決して大企業が真似することのできない、あなただけの最強の武器です。この武器を眠らせたままにするのは、あまりにももったいない機会損失と言わざるを得ません。
今こそ、頭の中にある想いを「言葉」にし、発信という形で世に送り出してください。 その一歩が、競合との不毛な価格競争を終わらせ、理想の顧客やバイヤーを惹きつける「選ばれる理由」へと変わっていくのです。
次なる一歩へ【「良い商品」を“売れる形”に変えるための第一歩】
今日ご紹介した「発信力の仕組み化」は、「良い商品」を「売れる商品」に変えるための重要な一歩です。しかし、発信力だけでは不十分です。発信が効果を発揮し、それが継続的な売上へと繋がるには、その裏側に「売り方の根本」となる確固たる戦略設計が必要です。
特に食品業界においては、顧客との深い関係性を築き、価格競争に巻き込まれにくい「ギフト」という領域が、この「売り方の根本」となる戦略設計の核となることが多いのです。
もし、この記事を読んで、「発信は分かったが、自社の『売れる仕組み』が本当にこれで良いのか不安」「特に、ギフト事業での課題を根本から見直したい」と感じた方に、無料のギフト課題チェックをご用意しました。
課題が見えることで、次の一手も明確になります。
未来の成果につなげるために、ぜひご活用ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
あなたのギフトビジネスが着実な成果に繋がることを、心より願っています。