
ギフト通販業界で18年、MD・バイヤーとして1,000社以上の企業様とお取引を重ね、数々のヒット商品を手がけてきました。
今は、その知見を活かし、食品メーカー様のギフト事業を“売れる形”にするお手伝いをしている内田です。
今日は、原材料の高騰が続く今、中小食品会社がなぜギフト事業に注力すべきなのか「利益を確保できる構造」という視点から、5つの理由に分けてお話ししていきます。
- 1. 食品メーカーの今、抱えている共通の悩み
- 1.1. 「安さ」だけでは疲弊する未来
- 2. この記事でわかること
- 3. 「ギフト市場」の可能性
- 3.1. 数字が示すギフト市場の安定性と高付加価値化
- 3.2. なぜ自家需要では利益が薄くなるのか?
- 4. 原材料高騰の今こそ!中小食品メーカーがギフト事業を強化すべき5つの理由
- 4.1. 1. 価格が上がっても「贈らない」という選択肢を取りにくい
- 4.2. 2. 価格より「質」や「特別感」が重視されやすい
- 4.3. 3. 「感情的価値」に支えられている市場である
- 4.4. 4. 包装や演出による“全体価値”で勝負できる
- 4.5. 5. ギフトの需要は年間を通じて多層的に存在する
- 5. 成功と失敗から学ぶ「ギフト設計のズレ」
- 5.1. 成功例 「物語」をギフトにした老舗醤油蔵
- 5.2. 失敗例 「中身は完璧、外は無関心」だった高級パスタソースメーカー
- 6. 疲弊から解放されるためのギフト事業3ステップ
- 6.1. ステップ1:「誰が、誰に、何を贈るのか」を徹底的に絞り込む
- 6.2. ステップ2:「感情的価値」を増幅させる包装と演出設計
- 6.3. ステップ3:販売チャネルを「高利益」構造に適応させる
- 7. FAQ(よくある質問) ギフト事業の疑問を解消
- 7.1. Q1:ギフト商品の適正な価格設定の目安は?
- 7.2. Q2:SNSでの「カジュアルギフト」のトレンドにも対応すべきですか?
- 7.3. Q3:ギフト対応で最もトラブルになりやすいのは何ですか?
- 8. 価格競争から脱却するための「無料ギフト課題診断」
- 9. まとめ【価格競争から脱却するために】
食品メーカーの今、抱えている共通の悩み

中小食品メーカーの経営者であるあなたが今、日々感じている経営のプレッシャーは、私にも痛いほど伝わってきます。
原材料、物流、人件費、あらゆるコストが上がり続ける中、「良いものを作っても儲からない」という構造的な問題に、多くの企業が直面しています。
このままでは、皆さんの「こだわりの味」が、「価格競争」という波に飲まれてしまいかねません。
「安さ」だけでは疲弊する未来
いきなりですが、今、中小食品メーカーの経営者の皆さんから、本当に多くのお悩みを耳にします。
「このままだと、利益がジリ貧になってしまう…」
2025年に入っても、原材料費、物流費、人件費の高騰の波は一向に収まりません。円安の影響も重なり、コストは上がる一方なのに、皆さんが主に扱う自家需要(ご自宅用)の商品では、そう簡単に販売価格に転嫁できないのが現実です。
- 「ライバルも価格を抑えているから、値上げしたらお客様が離れてしまうんじゃないか?」
- 「かといって、このままでは利益が確保できない。むしろ赤字になりかねない…」
- 「一生懸命良いものを作っているのに、価格競争に巻き込まれて疲弊している…」
これが、今、多くの真面目な食品メーカーさんが共通して抱えている最大の課題ではないでしょうか?
あなたが本当に望んでいるのは、適正な利益を確保しながら、こだわりを持って作った価値ある商品を、正当に評価してくれるお客様に届けることです。
しかし、自家需要の販路では、どうしても「安さ」が一番の決定打になりがちで、結果として「売上は上がっているけど、手元に残る利益が少ない」という“疲弊スパイラル”に陥ってしまっていませんか?
この記事でわかること
- 原材料高騰の波を乗りこなすための、ギフト市場特有の「利益を確保できる構造」がわかります。
- 自家需要とギフト需要の決定的な購買心理の違いを理解し、高単価で販売するための具体的な戦略を知ることができます。
- 成功事例・失敗事例、チェックリストを通して、あなたの会社が今すぐ取り組むべきステップが明確になり、疲弊から解放される道筋が見えます。
私自身、この業界にいて痛感してきたのは、「ギフトは単なる商品ではなく、感情を運ぶ手段である」ということです。この「感情的価値」に支えられているからこそ、食品メーカーさんは、この市場で疲弊することなく、適正な利益を確保できるのです。
「ギフト市場」の可能性
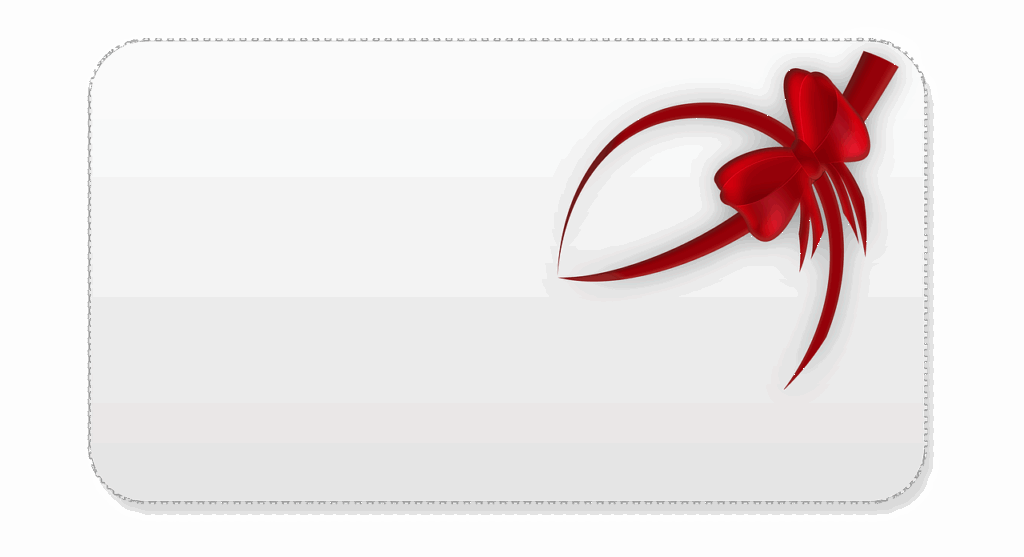
数字が示すギフト市場の安定性と高付加価値化
まず、私たちが今、目を向けるべきギフト市場の構造を見てみましょう。
- 市場規模の安定性
矢野経済研究所の調査などによると、国内ギフト市場規模はコロナ禍を経て回復し、10兆円超で安定的に推移しています。
これは、日本に深く根付いた贈答文化(お中元、お歳暮、結婚、出産、誕生日など)に支えられており、景気の変動に比較的左右されにくいことを示しています。
特に、近年は親しい間柄で気軽に贈り合うカジュアルギフトや、SNSを介したソーシャルギフトの需要も加わり、市場を多層的に支えています。 - 客単価の傾向
一般的に自家需要品の平均客単価が1,000円〜3,000円程度であるのに対し、ギフト市場の平均客単価は3,000円〜5,000円以上と高くなる傾向があります。
この客単価の高さが、利益確保の大きな鍵となります。
ギフトでは「プライスライニング」(3,000円、5,000円、10,000円など段階的な価格設定)が一般的であり、これにより購入者は予算に合わせた高単価商品を選びやすくなります。 - 収益性の課題
一方で、農林水産省や財務省のデータを見ても、食品製造業全体の売上高営業利益率は、原材料高騰の影響で製造業全体の平均よりも低い水準にあります。
売上自体は回復傾向にあっても、原価率の上昇によって収益性については大幅に悪化していることがわかります。
なぜ自家需要では利益が薄くなるのか?
自家需要の販売は、基本的に「コストパフォーマンス(コスパ)」が判断基準です。原価が上がれば、利益を維持するためには販売価格を上げるか、どこかのコストを下げるしかありません。
特に食品はコモディティ化が進みやすく、消費者は価格に敏感になりがちです。
この構造が、皆さんが「良いものを作っても儲からない」と感じる最大の理由です。価格を上げればお客様は競合に流れ、価格を据え置けば利益が目減りする、という袋小路に入ってしまいます。
しかし、ギフト市場では購買行動が全く異なります。ギフトの判断基準は「相手への想い」であり、価格は二次的な要素となるため、自家需要の「価格の縛り」から解放され、利益を確保できる構造に移行できるのです。
原材料高騰の今こそ!中小食品メーカーがギフト事業を強化すべき5つの理由

ギフト事業に注力すべき5つの理由を、「利益を確保できる構造」という視点から深掘りします。これこそが、価格高騰の波を乗りこなすための具体的な勝ち筋です。
1. 価格が上がっても「贈らない」という選択肢を取りにくい
ギフトは、価格競争を超えた「人間関係」で支えられている市場です。
自家需要(自分のため)の買い物は、値上がりすれば「今回は我慢しよう」「他で代用しよう」という選択肢を容易に取れます。しかし、ギフトはそうはいきません。
- 社会的・文化的な必須性
お中元、お歳暮といった季節の贈答や、結婚祝い、出産祝いなどのライフイベントにおけるギフトは、社会的なマナーや文化として根付いています。多少価格が上がっても「贈らない」という選択は、人間関係や社会的な信用に関わるため、贈り主は価格上昇を許容する傾向にあります。 - 需要の安定
この「贈らない」選択肢を取りにくい特性が、価格上昇が需要を大きく落としにくい、年間を通じて比較的安定した収益源を確保できる要因となります。
2. 価格より「質」や「特別感」が重視されやすい
ギフトの目的は「喜び」であり、「安さ」は判断基準になりません。
- 高付加価値化の許容
贈り主は「相手に喜んでもらうこと」「自分の気持ちを正しく伝えること」を最優先します。そのため、単なる安さではなく、「質」「ストーリー」「希少性」「限定感」といった付加価値に、ためらいなく投資します。 - 高単価への移行
皆さんがこだわって作った高単価な商品やプレミアムラインを、正当な価格で販売しやすくなります。自家需要で苦労していた「値上げの壁」が、ギフトでは「価値への対価」として受け入れられやすくなるのです。
3. 「感情的価値」に支えられている市場である
ギフトの売買の中心にあるのは「感謝」や「思いやり」といった感情です。
- 購買動機の中核
ギフトは、単なる食品という「モノ」の売買ではなく、「気持ち」を届けるコミュニケーション手段です。「この商品を選んだのは、あなたの健康を考えて」「あの時のお礼の気持ちです」といった感情的価値が、購買を決定づける中心になります。 - 価格訴求からの脱却
感情的価値が優先されることで、価格は二次的な要素となるため、「価格が安いから売れる」という消耗戦から完全に脱却し、「価値が高いから選ばれる」という理想的な仕組みを作りやすくなります。
4. 包装や演出による“全体価値”で勝負できる
同じ商品でも、「外側」の演出で商品の価値は2倍にも3倍にもなります。
- トータルパッケージの力
ギフト商品は、中身の食品だけでなく、包装紙、高級感のある箱、熨斗(のし)、メッセージカード、しっかりとした商品説明書など、付随する「演出」もすべて商品の価値に含まれます。- <具体例> 中身の原価は同じ4,000円相当の食品でも、高級和紙箱とメッセージカードをつけて5,000円で売ったほうが、ギフトとしては「相手への配慮」として価値が高まり、売れます。
- <具体例> 中身の原価は同じ4,000円相当の食品でも、高級和紙箱とメッセージカードをつけて5,000円で売ったほうが、ギフトとしては「相手への配慮」として価値が高まり、売れます。
- 利益率の確保
包装コストをかけても、販売価格を適切に上乗せすれば、実質的な原価率を改善し、結果的に高い利益率を確保できます。重要なのは、「価格以上の満足感」を受け取り手と贈り主の双方に感じてもらうことです。
5. ギフトの需要は年間を通じて多層的に存在する
特定シーズンに限定されない、多様な購入動機が市場を支えています。
- 多角的な需要
伝統的なお中元、お歳暮に加え、結婚・出産・新築祝いなどのライフイベントギフト、そして近年急増しているパーソナルギフト(誕生日、お礼、手土産)が、年間を通じて発生しています。 - 経営の安定化
これらの多様なニーズにきめ細かく対応することで、売上のピークとオフピークの差を埋め、年間を通じて安定したキャッシュフローを生み出しやすくなります。これは、原材料高騰によるコスト増を吸収する上で、非常に重要な経営基盤となります。
成功と失敗から学ぶ「ギフト設計のズレ」
ギフト事業で利益率を向上させる企業と、自家需要の感覚から抜け出せず伸び悩む企業には、明確な「ギフト設計のズレ」があります。
成功例 「物語」をギフトにした老舗醤油蔵
ある老舗の醤油蔵は、自家需要向けでは価格競争に疲弊していました。しかし、ギフト事業でV字回復を果たしました。
- 【施策】
- ターゲット設定:
「食通な親世代への贈り物」に絞り込み。 - 商品の転換
通常の醤油ではなく、「限定生産」「二年熟成」の最高級品を、小瓶に詰めたギフト専用セットを開発。 - 演出の徹底
醤油の「蔵の歴史」「職人の想い」「製造工程の物語」を丁寧に記載した高級感のある小冊子を同梱。さらに、「この醤油に合う料理」を提案するレシピカードを季節ごとに変更。
- ターゲット設定:
失敗例 「中身は完璧、外は無関心」だった高級パスタソースメーカー
- 【課題】 最高品質の素材を使ったパスタソースでしたが、ギフトセットは汎用的な白い段ボール箱に商品が並んでいるだけ。
- 【原因】 贈り主が「大切な人への贈り物」として購入する際、**外見の「特別感」や「高級感」**が欠けていました。特にフォーマルなシーンでは、「相手に贈るには少しカジュアルすぎる」と判断され、購入候補から外れてしまいました。
- 【学び】 ギフトは「中身」と「外側の演出」が二馬力で価値を生み出します。品質に自信があるなら、その価値を伝えるための「最高の舞台」(パッケージ)に、投資を惜しんではいけません。
疲弊から解放されるためのギフト事業3ステップ

ここからは、あなたが今すぐ実行できる具体的なステップを3つに整理します。
ステップ1:「誰が、誰に、何を贈るのか」を徹底的に絞り込む
「万人受け」のギフトは結果的に「誰からも選ばれない」ものになりがちです。「誰が(贈り主)、誰に(受け取り手)、どんな気持ちを(シーン)」贈りたいのかを明確にしましょう。
| 質問事項 | ギフト設計の目的とポイント |
| 誰が(贈り主)? | 例:法人の広報担当者、30代の娘、60代の孫の祖母など、購買層の悩みを深く理解する。 |
| 誰に(受け取り手)? | 例:健康志向の高い上司、離れて暮らす両親、小さな子供がいる家族など、相手のニーズを具体化する。 |
| 贈るシーンは? | 例:結婚内祝い、ビジネスのお礼、帰省土産、誕生日。シーンによって価格帯と求められるマナーが異なります。 |
| 商品選定 | 自家需要では買えない、少し贅沢で特別な商品をギフト専用として選び、既存商品との差別化を図る。 |
ステップ2:「感情的価値」を増幅させる包装と演出設計
商品の価値を最大限に高め、「価格以上の満足感」を受け取り手と贈り主の双方に提供します。この「演出」こそが、高単価を正当化する最大の理由です。
- パッケージのグレードアップ
- 素材
高級感のある紙箱、木箱、または重厚な色合いの専用パッケージを採用する。 - デザイン
ブランドの世界観を表現しつつ、贈答品として「格」を感じさせるデザインにする。
- 素材
- マナー対応の徹底
- 熨斗(のし)
紅白、結び切り、蝶結びなど、シーンに合わせた熨斗を正確に選び、名入れにも対応できる体制を整える。 - 同梱物
お届け先に価格がわかる明細書(納品書)を同梱しないよう、出荷プロセスで二重チェックを義務付ける。これは贈り主の信用に関わる最重要事項です。
- 熨斗(のし)
- メッセージとストーリーの付加
- メッセージカード
贈り主の気持ちを代弁する手書き風メッセージカードのオプションを必須とする。 - ブランドブック
商品のこだわりやストーリーを伝える小冊子、蔵の歴史といった「物語」を記載した小冊子を必ず同梱し、商品への納得感と食べる楽しみを提供する。
- メッセージカード
ステップ3:販売チャネルを「高利益」構造に適応させる
価格比較が激しいチャネルから離れ、「ギフト」として評価される場所に注力します。
- 販路のシフト
百貨店オンラインストア、法人ギフト専門ECサイト、ソーシャルギフトサービス、そして自社ECサイト内の「ギフト専用ページ」を強化します。 - 自社ECの強化
「ギフト」という単語で検索してきたお客様が迷わないよう、サイトのUI/UXを改善。熨斗の選択肢、メッセージカードのプレビュー、複数配送先の指定などを、ストレスなく行えるように設計します。 - コミュニケーション
「お得」「安い」ではなく、「大切な人への感謝」「健康を願う」「失敗のない贈り物」といった感情的なメッセージを中心に発信し、ギフトを求めるお客様の不安を解消する情報提供を徹底します。
FAQ(よくある質問) ギフト事業の疑問を解消

Q1:ギフト商品の適正な価格設定の目安は?
A:価格は「コスト」ではなく「価値」から逆算し、自家需要品より高い利益率を確保できる水準を目指しましょう。
ギフト市場では、自家需要品と比べ、原価に包装・演出コストと高い利益を上乗せすることが可能です。まずは、「お客様が贈答用として予算を組みやすい」3,000円、5,000円、10,000円といった価格帯(プライスライニング)を設定し、その価格で提供できる「全体価値」(中身の品質+包装+サービス)を設計しましょう。
重要なのは、価格設定の基準を「競合」ではなく「あなたが提供する価値」に置き、自家需要品よりも確実に高い収益性を確保することです。この構造こそが、原材料高騰の波を乗り越えるための生命線となります。
Q2:SNSでの「カジュアルギフト」のトレンドにも対応すべきですか?
A:はい。若年層の新規顧客獲得の窓口として活用し、パーソナライズを重視してください。
近年、ソーシャルギフト(e-Gift)など、SNSやメールで気軽に贈るカジュアルギフト市場が拡大しています。これは主に若年層がけん引しており、「ちょっとしたお礼」や「ねぎらい」として日常的に利用されます。
高単価を狙うだけでなく、このカジュアルな接点から、将来的にフォーマルなギフトを購入してくれる顧客層を育成することも重要です。
Q3:ギフト対応で最もトラブルになりやすいのは何ですか?
A:熨斗(のし)の間違いや配送先住所のミス、そして「在庫切れ」です。
ギフトの繁忙期(お中元、お歳暮)は、注文が集中し、物流コストも上がります。この時期に「在庫切れ」や「納期遅延」を起こすと、贈り主の「信用」を傷つけるだけでなく、次年度の購入にも響きます。
対策
繁忙期は特に余裕を持った在庫確保と、出荷体制(梱包・マナーチェック)の強化に最大限のリソースを割いてください。
価格競争から脱却するための「無料ギフト課題診断」
さて、このコラムをここまで読んだあなたは、「価格競争から脱却できるヒント」はつかめたはずです。しかし、「具体的にうちの会社は何から手をつければいいのか?」という疑問が残っているかもしれません。
ここで重要なのは、「あなたの会社のギフト設計の“ズレ”を正確に把握する」ことです。このズレが解消されない限り、どんなに良い商品でも、利益を確保できる構造にはなりません。
そこでギフト課題チェックリストをご用意しました。
3分で直感的に答えるだけで
- 改善すべきポイントが一目でわかる
- ギフトが自社に本当に有効かを判断できる
- 自己判断では気づけなかった“売れない原因”が明らかになる
ご利用者様からは
「チェックしただけで、自社の弱点がはっきりしました」
「診断レポートで改善の方向性が明確になり、次の一手が見えました」
といったお声をいただいています。
課題が見えることで、次の一手も明確になります。
未来の成果につなげるために、ぜひご活用ください。
まとめ【価格競争から脱却するために】
このコラムで見てきた通り、原材料高騰という逆風の中、中小食品メーカーさんが価格競争の波から脱出し、安定した利益を確保するために、ギフト事業に注力すべき5つの理由と具体的な勝ち筋をお話ししました。
ギフト市場は、あなたの「こだわり」と「品質」を正当に評価し、適正な利益をもたらしてくれる、最高の販路となり得ます。ギフトは単なる商品の詰め合わせではなく、企業としての売上構造を根本から変える、ビジネスモデルの転換点です。
「無料診断を受ける」という具体的な行動こそが、価格競争の疲弊から解放され、利益を確保できる構造を手に入れるための最初の一歩です。
未来の成果につなげるために、ぜひ今すぐギフト課題チェックリストを試してみませんか?
今日も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
あなたのビジネスが大成功すること
をいつも応援しています。


