
お忙しい中、ご覧いただきありがとうございます。
ギフト通販業界で18年、バイヤー・商品企画として1,000社以上の食品会社様とお取引を重ね、数々のヒット商品を手がけてきました。
今は、その知見を活かし中小食品会社様のギフト事業を“売れる形”にするお手伝いをしている内田です。
今日は「新規事業「担当者任せ」はもう失敗しない!社長の正しい関与で成功へ導く3原則」についてお話しします。
- 1. なぜ「新規事業」はいつも途中で立ち消えになるのか?
- 1.1. この記事でわかること
- 2. 社長の「不在」が招く3つの致命傷
- 2.1. 意思決定の遅延と機会損失
- 2.2. 既存組織からの「嫉妬」と「資源の横取り」
- 2.3. 「失敗の隠蔽」と「学びの停止」
- 3. 新規事業成功のための「社長の正しいコミットメント」3原則
- 3.1. 撤退ラインと許容損失額を「社長の責任」で明確化する
- 3.2. 「権限の範囲」と「社長の役割」を明文化する
- 3.3. 既存事業の「論理」から新規事業を完全に隔離する
- 4. 新規事業を軌道に乗せるための4つの実践チェックリスト
- 5. FAQ(よくある質問)と専門家からのアドバイス
- 5.1. Q1:「丸投げ」と「権限委譲」の違いは何ですか?
- 5.2. Q2:優秀な人材に任せれば、社長のコミットメントは不要ではないですか?
- 5.3. Q3:新規事業の進捗報告は、どれくらいの頻度で行うべきですか?
- 6. まとめ【新規事業の成功は「社長の関わり方」で決まる】
- 6.1. 高収益なギフト戦略への最初の一歩
なぜ「新規事業」はいつも途中で立ち消えになるのか?
「『次世代の柱を育てろ』と号令をかけたが、担当者のモチベーションが続かず、いつの間にか企画書が机の奥に眠っている」「既存事業の片手間で新規事業を進めているので、本業が忙しくなるとストップしてしまう」「初期投資はしたものの、追加の予算や権限を出すタイミングが分からず、ずるずると機会損失している」
もしあなたが、このような「新規事業の頓挫」というジレンマに悩んでいるなら、それは「任せ方」に致命的な欠陥があるからです。
多くの社長様は、新規事業を立ち上げる際、「優秀な担当者」を選び、「これは君に任せるよ」と一言で済ませてしまいがちです。しかし、新規事業の本質は「不確実性との戦い」であり、「既存の常識が通用しない場所」での挑戦です。この極めてリスクの高い戦いを、予算と権限が既存事業の常識に縛られた「一担当者」に「丸投げ」することは、その新規事業を立ち上げ前に潰していることに等しいのです。
- 新規事業の真実
新規事業の失敗原因の多くは、アイデアの質ではなく、「社長のコミットメント不足」と「意思決定スピードの遅さ」にあります。これは、担当者個人の力量では決して解決できません。
この記事でわかること
- 新規事業を失敗させる「丸投げ」の構造的欠陥と、担当者の思考停止が起きるメカニズムが分かります。
- 社長が本当に注力すべき「コミットメントの質」が明確になり、時間とリソースの無駄遣いを防げます。
- 新規事業を成功させるための「予算」「権限」「撤退ライン」の正しい設定方法が手に入ります。
社長の「不在」が招く3つの致命傷
中小企業の新規事業は、90%以上が失敗に終わるとも言われます。この高い失敗率の裏側には、社長の「丸投げ」から派生する、共通した3つの構造的欠陥があります。
意思決定の遅延と機会損失
新規事業は、顧客の反応や市場の変化に合わせて、毎日、毎週、意思決定と方向修正(ピボット)を繰り返す必要があります。
- 丸投げの悪影響
担当者は「新しいこと」をやるため、予算の1円、販促の1つに至るまで、既存事業を管轄する上層部や経理部門の承認を必要とします。上層部は既存事業の安定を優先するため、新規事業への承認は遅れがちです。 - 結果
2〜3日かかる承認待ちの間に、市場のトレンドは変わり、競合は先行し、担当者のモチベーションは急降下します。意思決定が遅れることによる「機会損失」は、新規事業の最大の敵です。
既存組織からの「嫉妬」と「資源の横取り」
新規事業には、既存事業にはない特別な予算や優秀な人材が割り当てられがちです。
- 丸投げの悪影響
社長が深く関与していないと、既存事業のマネージャーは新規事業を「本業のリソースを吸い上げる敵」と認識します。「なぜうちの事業の利益を、まだ売上もない新規事業に使うのか」という声が社内で上がり、担当者は孤立します。 - 結果
新規事業に必要な「社内の協力(製造ラインの調整、営業のサポートなど)」が得られなくなり、リソースを横取りされ、新規事業の推進力が完全に停止します。
「失敗の隠蔽」と「学びの停止」
新規事業は、「テストと失敗」の繰り返しを通じて、「売れる解」を探すプロセスです。
- 丸投げの悪影響
社長が新規事業の『進捗』ではなく、『結果』だけを求めていると、担当者は「失敗を報告すると怒られる」と感じます。 - 結果
担当者は「小さな失敗」を隠蔽し、「学ぶべき真実のデータ」が社長の元に届かなくなります。市場から得た貴重なフィードバックが活かされず、試行錯誤のプロセスが停止し、新規事業は「成功するまで失敗を繰り返す」という本質的なステップを踏めなくなります。
新規事業成功のための「社長の正しいコミットメント」3原則

「丸投げ」を防ぎ、最小の関与で最大の推進力を生むために、社長が集中すべき3つのコミットメント領域を解説します。
撤退ラインと許容損失額を「社長の責任」で明確化する
新規事業は、「いつまで」「いくらまでなら失敗していいか」のルールがないと、誰も挑戦できません。
- 社長のコミットメント内容
- 試行錯誤期間の設定
「この事業は〇〇年(例:3年)までは、利益が出なくても継続する」という時間軸を明確にする。 - 許容損失額の明示
「この事業で最大〇〇万円までの赤字(失敗)は、会社が学びとして受け入れる」という金額を明確にする。
- 試行錯誤期間の設定
- 効果
担当者は「この枠内なら、失敗を恐れず挑戦していい」という心理的安全性を得て、意思決定のスピードが爆発的に向上します。
「権限の範囲」と「社長の役割」を明文化する
担当者には「決める権利」を、社長には「社内の壁を壊す役割」を明確に定義します。
- 担当者への権限委譲
- 予算権限
「100万円までのテスト予算は、社長に相談なく自由に使っていい」といった即決できる予算を与える。 - 意思決定権
「販促施策やパッケージの$A/B$テストの結果に基づく方向転換は、担当者の判断で進める」と宣言する。
- 予算権限
- 社長の役割(コミットメント)
- 壁壊し
既存事業とのリソースやルールの衝突が発生した場合、社長が24時間以内に裁定を下すことを社内に宣言する。 - 進捗確認
『結果』ではなく、『学び』を問うために、月に1回、1時間の報告会を設け、「今週、最も大きな失敗から何を学んだか」だけを報告させる。
- 壁壊し
既存事業の「論理」から新規事業を完全に隔離する
新規事業は、既存事業の「成功体験」や「効率重視のルール」に縛られると失敗します。
- 組織上の隔離
新規事業チームを物理的に既存部門から離れた場所に設置するか、「別会社」に近い独立した会計・評価制度を適用する。 - 評価の隔離
新規事業の担当者を既存事業の『売上』や『利益率』で評価しない。初期段階では、「学習量(テスト回数)」「顧客からのフィードバック件数」「市場適合性の検証スピード」など、「努力と学びのプロセス」で評価する。
新規事業を軌道に乗せるための4つの実践チェックリスト
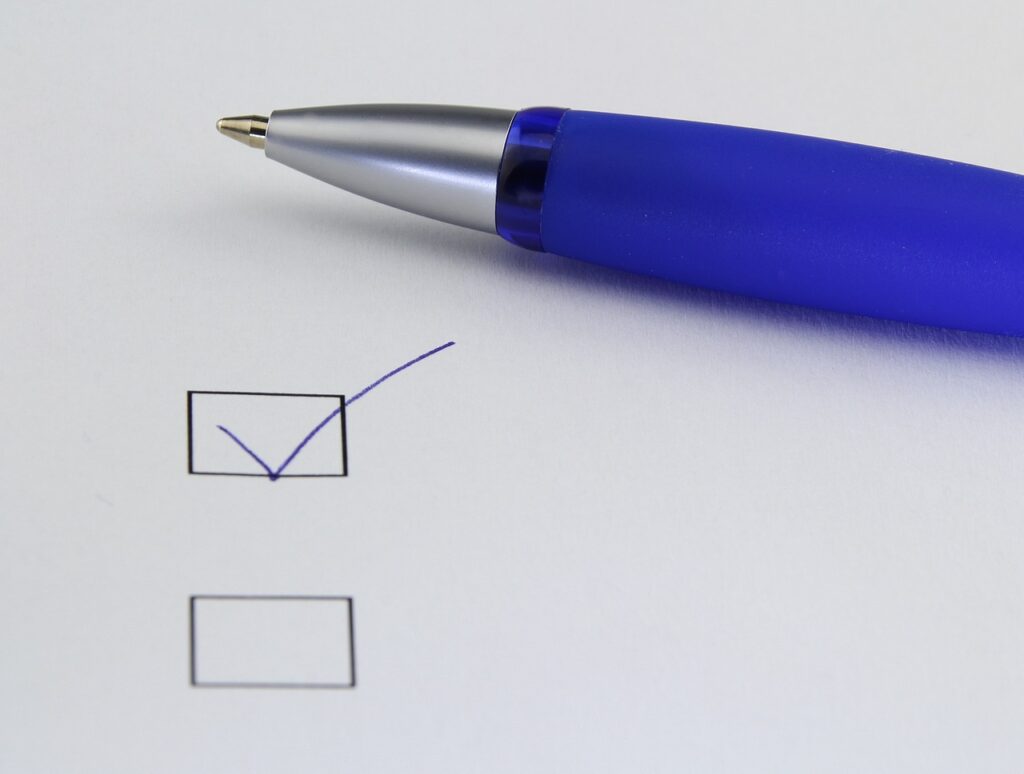
社長が新規事業を成功に導くために、自社の体制を客観的にチェックするための項目です。
| チェック項目 | 現状確認 | 改善の方向性 |
| 意思決定スピード | 担当者が「予算50万円の決裁」に何日かかっているか? | 即日決裁できる「実験用予算枠」を設ける。 |
| 既存事業の理解度 | 既存部門のマネージャーは、新規事業のMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を理解しているか? | 社長が全社集会で「新規事業が失敗しても、誰の責任にもしない」と公に宣言する。 |
| 担当者の権限 | 担当者は、既存事業のルールに縛られず、「既存商品の顧客リスト」や「製造ラインの2時間の空き」を自由に使える権限があるか? | 新規事業用に「1日1時間、製造ラインを貸し出す」など、特定のリソース確保を社長命令で保証する。 |
| 評価制度 | 新規事業担当者の評価が、本業の売上に引っ張られていないか? | 「3ヶ月間は売上ゼロでも満点」となるような『プロセス重視』の専用評価軸を導入する。 |
FAQ(よくある質問)と専門家からのアドバイス

Q1:「丸投げ」と「権限委譲」の違いは何ですか?
A:「権限委譲」は「枠組み(ルール)とコミットメント」を設定してから任せることです。
- 丸投げ
「これやっておいて」と責任だけを渡すこと。予算、権限、撤退ラインは曖昧。 - 権限委譲
「〇〇円の失敗までは許容する。判断はすべて任せる。ただし、1週間の学びは必ず報告せよ」と、リソースとルールを明示し、社長は最終的な責任のみを負うこと。
Q2:優秀な人材に任せれば、社長のコミットメントは不要ではないですか?
A:優秀な人材ほど「社内の壁」にぶつかり、モチベーションを失います。
優秀な担当者ほど、既存組織の非効率なルールや、他部署の非協力的な態度に敏感に反応し、「これでは勝てない」と見切りをつけます。彼らに必要なのは、社長の「壁を壊す」という後ろ盾です。社長が本気であることを示すことで、彼らは安心して「不確実な外部」との戦いに集中できます。
Q3:新規事業の進捗報告は、どれくらいの頻度で行うべきですか?
A:頻度は高く、しかし報告内容は「学び」に絞るべきです。
週に1回、15分〜30分の短い報告会を推奨します。社長は決して「どうすれば売れるか」という戦術的なアドバイスをしてはいけません。問うべきはただ一つ、「今週、市場から得られた最も価値のある『学び』は何だったか?」「その学びに基づいて、来週は戦略をどう変えるのか?」です。これにより、担当者は「結果」ではなく「試行錯誤」に集中できます。
まとめ【新規事業の成功は「社長の関わり方」で決まる】
本記事では、中小食品メーカーの新規事業が**「担当者任せ=社長の丸投げ」によって潰される構造と、社長がコミットメントと正しい権限委譲を行うことで、成功確率を飛躍的に高める戦略をお伝えしました。
- 新規事業の失敗の多くは、担当者の「権限不足」と「既存組織との衝突」に起因します。
- 社長は「撤退ライン」と「許容損失額」を明確にし、担当者に失敗を恐れない「心理的安全性」を与えるべきです。
- 『結果』ではなく『学び』を評価し、新規事業を既存事業の論理から隔離することが、成功の鍵です。
高収益なギフト戦略への最初の一歩
さて、「新規事業の失敗構造は理解できたが、次の収益の柱として何を狙うべきか」と、具体的な市場を模索しているあなたへ。
あなたが築き上げた「既存事業の信頼」や「独自の技術」**が最も高く評価され、価格競争から最も遠い高収益な市場、それがギフト市場です。
新規事業としてギフト市場に参入する、あるいは既存のギフト事業を高収益化させるには、社長の強いコミットメントが必要です。しかし、その『売り方』の土台、つまりギフト戦略の設計が整っていないと、せっかくの挑戦も既存事業の延長で終わってしまいます。
もしあなたが、この高付加価値市場で成功するための「売り方の根本」に課題を感じているなら、『ギフト戦略の設計』に着目したチェックリストをご活用ください。
このチェックリストは、商品や販促といった表面的な課題ではなく、売り方の根本=ギフト戦略の土台が整っているかを診断します。
課題が見えることで、次の一手も明確になります。未来の成果につなげるために、ぜひご活用ください。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
あなたのビジネスが成功することをいつも応援しています。


