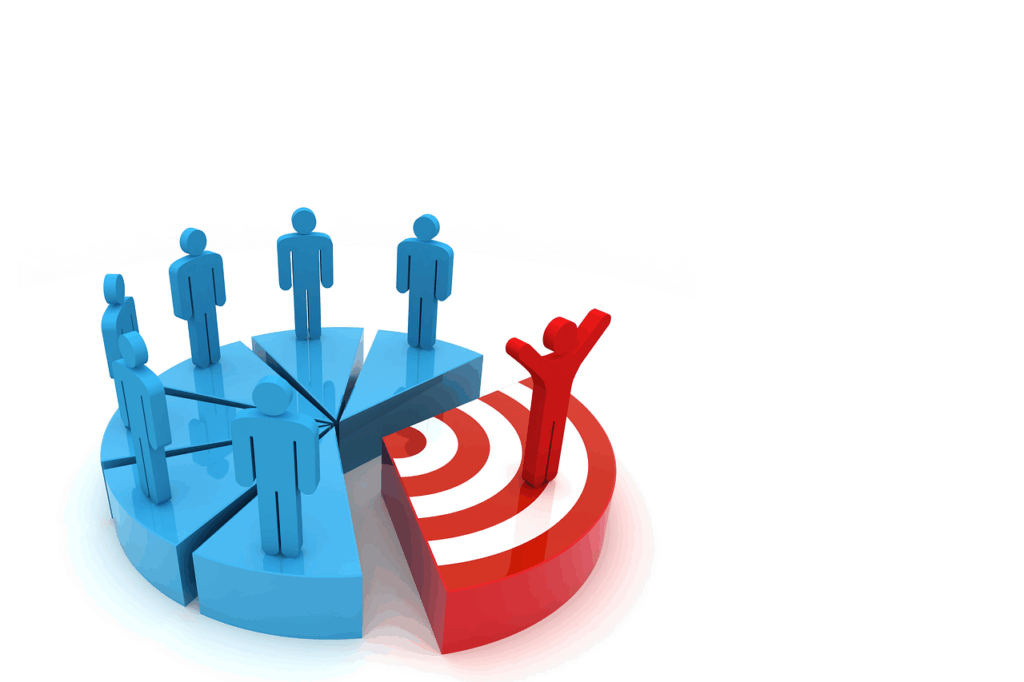
お忙しい中、
ご覧いただきありがとうございます。
ギフト通販業界で18年、MD・バイヤー
として1,000社以上の食品会社様とお取引を重ね、
数々のヒット商品を手がけてきました。
今は、その知見を活かし中小食品会社様のギフト
事業を“売れる形”にするお手伝いをしている内田です。
今回は「社長が知らない「ギフトが売れない」根本原因。ヒット商品を生むペルソナ設計とは」についてお話しします。
「ペルソナって聞いたことあるけど、実際どう役立つの?」
そんな疑問を持つ方に向けて、なぜペルソナがギフト商品開発において不可欠なのか、そして、どのように実践すれば良いのかを、お話しします。
- 0.1. 「ターゲット」と「ペルソナ」の違いを深く理解する
- 1. ペルソナがない商品は、なぜ売れないのか?
- 1.1. (1) 商品の軸がブレる
- 1.2. (2) 売り場や広告で「誰に刺さるのか」が不明確
- 1.3. (3) 競合商品との差別化が曖昧になる
- 2. ギフト開発は「贈る人」と「贈られる人」両方を描く
- 2.1. 事例1:上司に贈る「ちょっとした手土産」
- 2.2. 事例2:おしゃれな友人に贈る「誕生日プレゼント」
- 3. 共感できる商品が選ばれる理由
- 4. ペルソナ設計のステップ
- 4.1. ステップ1:データ収集
- 4.2. ステップ2:共通点を抽出
- 4.3. ステップ3:一人の人物像に落とし込む
- 4.4. ステップ4:贈る相手も具体化する
- 5. ペルソナ設計がもたらす効果
- 5.1. (1) 商品開発の軸が定まる
- 5.2. (2) 販促コピーが具体的になる
- 5.3. (3) 営業トークに一貫性が出る
- 5.4. (4) チームの意識が揃う
- 6. よくある失敗例と注意点
- 6.1. (1) 理想の顧客を描きすぎる
- 6.2. (2) 複数のペルソナを同時に狙う
- 6.3. (3) 設計後に放置する
- 7. まとめ【この商品は誰のためのものですか?】
- 8. 無料ギフト課題チェックリストのご案内
「ターゲット」と「ペルソナ」の違いを深く理解する
まず押さえておきたいのは、ターゲットとペルソナは似ているようで、その役割が全く異なるという点です。
- ターゲット
「30代の主婦、都市部在住、共働き」といった「属性のかたまり」 - ペルソナ
名前、年齢、家族構成、趣味、買い物の悩みまで具体的に設定した“たった一人”のモデル顧客
つまり、
ターゲット = ざっくりとした人の群像
ペルソナ = リアルな顔を持った一人
この違いを理解することが、売れる商品づくりの出発点です。
たとえば、ターゲットが「30代女性・既婚・子どもあり」だったとしても、ペルソナにすると以下のように全く異なる人物像が浮かび上がります。
- 仮名 佐藤彩子さん(35歳・東京都世田谷区在住・小学生の子ども2人・フルタイム勤務)
- ライフスタイル
仕事と子育てで忙しい毎日。平日はスーパーで買い物を済ませるが、週末は家族でカフェや商業施設に出かける。 - ギフトの習慣
季節の行事やママ友とのやりとりは大切にしている。贈り物は百貨店やネット通販をよく利用。 - ギフトの悩み
「失敗したくない」「センスよく見られたい」「相手に気を遣わせたくない」という気持ちが強く、毎回何を選ぶか悩む。 - 重視する点
価格帯は2,000~3,000円。常温で持ち運びやすく、個包装になっているものが理想。
- ライフスタイル
- 仮名 鈴木由美さん(32歳・福岡県福岡市在住・未就学児の子ども1人・育児休業中)
- ライフスタイル
子育て中心の生活。子どもが寝ている間にSNSで情報収集をするのが日課。 - ギフトの習慣
ママ友との「ちょっとした手土産交換」を頻繁に行う。贈り物はSNSで話題になっている商品や、おしゃれなパッケージのものに興味がある。 - ギフトの悩み
「他の人と被りたくない」「写真映えしないとつまらない」と感じている。 - 重視する点
3,000〜5,000円程度の、おしゃれで話題性のある商品。冷凍でも構わないが、見た目のインパクトは重視したい。
- ライフスタイル
このように、たった一人にまで具体化することで、開発会議での議論や広告コピーの方向性が一気に明確になります。
ペルソナがない商品は、なぜ売れないのか?
中小食品会社様からよく伺う声に、「商品は作ったけど反応が薄い」「ギフトECに載せても売れ行きが伸びない」というものがあります。
その原因の多くは「誰に向けた商品かが曖昧」になっていることです。
ペルソナが設定されていないと、以下のような問題が起こり、商品が市場に埋もれてしまいます。
(1) 商品の軸がブレる
会議で「この色が可愛い」「価格はこのくらいで」と、個人の主観に基づいた意見がバラバラに出てしまい、商品のコンセプトが定まりません。
しかし、「佐藤彩子さん(ペルソナ)に喜んでもらえる商品は何か?」
という共通の基準を持つことで、パッケージデザイン、価格設定、販売チャネルのすべてにブレが
なくなります。
チーム全体が同じ方向を向いて開発を進められるのです。
(2) 売り場や広告で「誰に刺さるのか」が不明確
お客様の目に留まるまでには、数秒しかありません。
その短い時間で「これは私のための商品だ」と感じさせなければ、すぐにページを閉じられてしまいます。
ペルソナが不明確だと、「どなたにでも喜ばれる贈り物です」といった抽象的な表現になりがちです。
しかし、ペルソナがあれば「仕事と子育てに忙しいあなたへ、特別な癒しの時間を贈るスイーツ」のように、お客様の心に響く具体的なメッセージを届けられます。
(3) 競合商品との差別化が曖昧になる
ペルソナがないと、競合と同じような商品を作ってしまい、価格競争に巻き込まれてしまいます。
例えば、「美味しいお煎餅」は世の中に無数に存在します。
しかし、ペルソナを「実家に暮らす祖母に贈る孫からの贈り物」と設定すれば、
- 「歯が悪い祖母でも食べやすい、柔らかいお煎餅」
- 「長年の感謝を伝える、高級感のある桐箱入り」
- 「懐かしい気持ちを思い出させる、昔ながらの素朴な味わい」
といった、明確な差別化ポイントが見えてきます。
ギフト開発は「贈る人」と「贈られる人」両方を描く
通常の商品開発では「使う本人」のことだけを考えれば済みますが、ギフトには「贈る人(購入者)」と「贈られる人(受け取る相手)」という、2つの関係性が存在します。
どちらか一方の視点だけでは、ギフトとしては成立しません。
例えば、「最高級の素材」にこだわった商品を作っても、贈る人が「こんなに高価なものを贈ったら、相手に気を遣わせてしまうかも」と感じれば、購入には至らないでしょう。
事例1:上司に贈る「ちょっとした手土産」
- 贈る側の心理
「気を遣わせず、でもきちんと感を出したい」「かさばらず、スマートに渡したい」 - 贈られる側の心理
「重たいお返しはしたくない」「みんなで分けられるものが嬉しい」 - 商品に求められること
2,000円前後の価格帯、高見えするパッケージ、常温保存可能、個包装。
事例2:おしゃれな友人に贈る「誕生日プレゼント」
- 贈る側の心理
「センスがいいと思われたい」「特別感を演出したい」「SNS映えさせたい」 - 贈られる側の心理
「自分では買わないような、特別なものが欲しい」「おしゃれなパッケージでテンションが上がる」 - 商品に求められること
3,000円〜5,000円程度の、限定感のある商品、デザイン性の高いパッケージ、開けた瞬間に驚きがある仕掛け。
このように、誰に贈るか、そしてどんな関係性かを具体的に描くことで、同じ商品でも方向性は大きく変わります。
共感できる商品が選ばれる理由
今のギフト市場は「似たような商品が大量にある」のが現実です。
そんな中で選ばれるのは、機能やスペックだけで選ばれる商品ではなく、
「この商品なら、あの人が喜びそう」
「このパッケージなら、このシーンで渡せる」
といった、共感の軸を明確に打ち出した商品です。
ペルソナを細かく設定することは、この共感を生むために不可欠です。
ギフト市場では、商品の背景にある「ストーリー」や「文脈」が価値を生み、結果として価格競争に巻き込まれない強い武器になります。
例えば、「ただのジャム」ではなく、「祖母の代から受け継いだ無農薬のイチゴを、一つひとつ手作業で煮詰めたジャム」
というストーリーがあれば、お客様は「これは単なるジャムではない。大切な人に贈るのにふさわしい」と感じてくれます。
ペルソナ設計のステップ
ここからは、実際に中小食品メーカー様がペルソナを作るときの流れを整理します。
ステップ1:データ収集
まずは、お客様に関する情報を集められるだけ集めます。
- 自社ECサイトや楽天、Amazonなどの購買履歴(性別、年代、居住地など)
- 過去のアンケートやレビュー(購入動機、感想、用途など)
- 百貨店や催事での売れ筋や、お客様との会話
- SNSでの自社商品に関する投稿や、競合商品のレビュー
ステップ2:共通点を抽出
集めたデータから、定量的な傾向を見つけ出します。
- 「購入者の80%が30〜40代女性」
- 「ギフト利用が70%を占める」
- 「商品レビューに『可愛い』『おしゃれ』という言葉が多い」 こうしたデータから、「デザインを重視する30代女性が、ギフトとして購入している」という共通点が見えてきます。
ステップ3:一人の人物像に落とし込む
抽出した共通点を基に、一人の人物像を具体的に描きます。
- 名前(仮名でOK)
- 年齢・家族構成
- 居住エリア
- 仕事・ライフスタイル
- ギフトを贈るシーン・悩み
この時、趣味や休日の過ごし方まで想像することで、よりリアルな人物像が生まれます。
ステップ4:贈る相手も具体化する
ギフト開発では、贈る側だけでなく、贈られる相手も具体的に描くことが重要です。
「彩子さんは、小学生の子どもがいるママ友に季節の贈り物をする」
「鈴木さんは、SNSで知り合った親友に、サプライズの誕生日プレゼントを贈る」
このように、シーンまで描くことで、商品の持つべき機能(個包装、日持ちなど)や、コミュニケーションの方向性(メッセージカードの文言など)がより明確になります。
ペルソナ設計がもたらす効果
ペルソナ設計をきちんと行うと、以下の効果が期待できます。
(1) 商品開発の軸が定まる
- 色・サイズ・価格設定の議論がスムーズに
「ペルソナの予算はこれくらいだから、この価格にしよう」「ペルソナが普段使うバッグに入るサイズにしよう」など、客観的な基準で意思決定ができます。
(2) 販促コピーが具体的になる
- 響くメッセージを届けられる
「忙しいママでも失敗しない手土産」のように、ペルソナの悩みに寄り添った、明確な打ち出しができます。
(3) 営業トークに一貫性が出る
- バイヤーへの説明が簡潔に
「この商品は誰向けか」を一言で説明できるため、取引先との商談がスムーズに進みます。
(4) チームの意識が揃う
共通言語でコミュニケーション
社内で「佐藤彩子さんに喜んでもらえるか?」を共通言語にすることで、部門間の連携が強化されます。
よくある失敗例と注意点
ペルソナ設計をしても失敗するケースもあります。
(1) 理想の顧客を描きすぎる
- 注意点
実際には存在しないような「完璧な顧客像」を描いてしまうと、現実離れした商品になり、誰にも買ってもらえません。データに基づき、現実的な人物像を描くことが大切です。
(2) 複数のペルソナを同時に狙う
- 注意点
「上司への贈り物にも、友人への贈り物にも使える商品」を目指すと、結局どっちつかずの商品になります。まずは一人に絞り込み、その一人を徹底的に喜ばせる商品を作るのが鉄則です。
(3) 設計後に放置する
- 注意点
市場や顧客の嗜好は常に変化します。一度作ったペルソナも、年に一度はデータを見直し、最新の状態にアップデートする必要があります。
まとめ【この商品は誰のためのものですか?】
ペルソナ設計は単なるマーケティング用語ではありません。
「誰の、どんな悩みを解決する商品か?」
を明確にすることは、
- 開発の軸をぶらさない
- 販促で一貫したメッセージを打ち出せる
- 価格競争に巻き込まれない といった、成果につながります。
もし今のギフト事業に手ごたえを感じていないなら、一度立ち止まり、あなたの商品のペルソナ設計が曖昧になっていないか見直してみてください。
無料ギフト課題チェックリストのご案内
「ギフト事業で思うように成果が出ない…」
そんなお悩みをお持ちの中小食品メーカーの経営者の方へ。
“今のギフト事業にどんな課題があるのか”を確認できる 【ギフト課題チェックリスト】をご用意しました。
課題が見えることで、次の一手も明確になります。
未来の成果につなげるために、ぜひご活用ください。
今日も最後までお読みいただき
ありがとうございました。
あなたのビジネスが成功すること
をいつも応援しています。


